採用戦略の立て方とは?中小企業が成功するための5ステップと具体例を解説
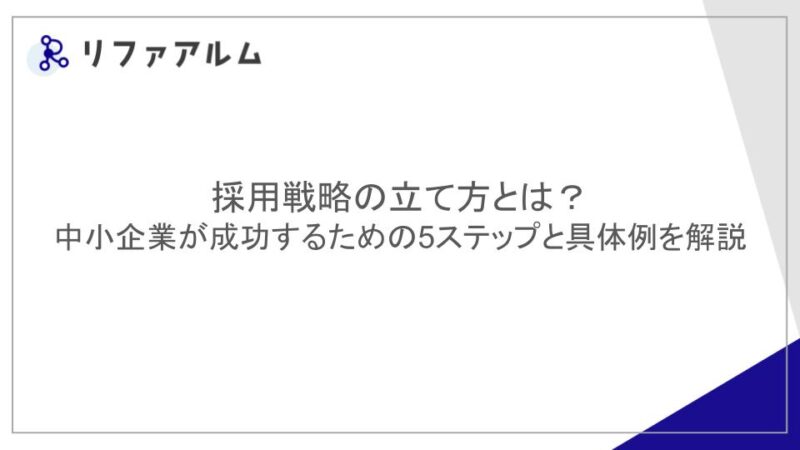
「以前に比べて、求人を出しても応募が集まらない」「採用人数は変わらないのに、採用コストだけが増え続けている」「内定を出しても辞退されてしまう」「せっかく採用しても、ミスマッチですぐに辞めてしまう」
企業の経営者様や人事担当者様とお話ししていると、このような採用に関する切実な悩みを多く伺います。もし、貴社がこれらの課題を抱えているとしたら、それは「採用活動」が場当たり的になっており、一貫した「採用戦略」が不在であることが原因かもしれません。
この記事では、採用に悩む経営者・人事担当者の皆様に向けて、なぜ今、採用戦略が重要なのか、そして「採用戦略の立て方」を具体的な5つのステップで分かりやすく解説します。
もくじ
なぜ今、採用戦略が重要なのか?その背景を解説
まずは、「採用戦略」の重要性について、深く掘り下げてみましょう。
「戦略」と聞くと難しく感じられるかもしれませんが、「採用活動」との違いで考えると分かりやすいです。
- 採用活動(戦術)
・目の前の採用課題を解決するための具体的な「手段」です。
(例:求人広告を出す、人材紹介会社に依頼する、面接を実施する) - 採用戦略(戦略)
・採用活動全体を成功に導くための「計画」であり、「方針」です。
(例:いつまでに、どんな人材を、何人、どのチャネル(手段)で、どのようなメッセージで魅力付けして採用するか)
戦術(採用活動)ばかりに目が行き、戦略(採用戦略)が曖昧だと、「どの求人媒体が効果的か」という手段の議論に終始してしまい、根本的な課題が解決されません。
採用戦略の重要性が増している3つの背景
では、なぜ今、これほどまでに「採用戦略」が重要視されているのでしょうか。主に3つの背景があります。
1. 労働人口の減少と採用競争の激化
ご存知の通り、日本は深刻な人手不足の時代に突入しています。特に生産年齢人口(15~64歳)は減少し続けており、企業間での優秀な人材の奪い合い(採用競争)は激化する一方です。従来のように「待っている」だけでは、応募すら集まらない時代になりました。
2. 働き方の多様化と求職者の価値観の変化
リモートワークの普及や副業・兼業の一般化など、働き方は大きく変化しました。求職者が企業に求めるものも、「給与」や「安定」だけでなく、「やりがい」「カルチャーフィット」「柔軟な働き方」など、非常に多様化しています。「自社が求める人材は、何を重視しているのか」を深く理解し、的確にアプローチする戦略が不可欠です。
3. 採用ミスマッチによる早期離職コストの増大
採用競争が激しいからといって、「誰でもいいから採る」という方針をとってしまうと、入社後のミスマッチによる早期離職につながります。一人の社員を採用し、教育し、戦力化するまでには多大なコスト(採用費、人件費、教育費)がかかります。この隠れたコストを最小限に抑えるためにも、戦略に基づいた「質の高いマッチング」が求められています。
採用戦略の立て方5ステップ
ここからは、本題である「採用戦略の立て方」を、実践的な5つのステップで具体的に解説します。ぜひ、自社の状況に当てはめながら読み進めてください。
経営戦略・事業計画の確認
採用戦略は、経営戦略や事業計画を実現するための「手段」です。決して、採用が独立して存在するわけではありません。
まずは、自社の「ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)」や「中期経営計画」を再確認してください。
- 会社は今後、どの方向に進もうとしているのか?
- どの事業に注力し、どれくらい成長させる計画なのか?
- そのために「なぜ」採用が必要なのか?(事業拡大、新規事業立ち上げ、組織体制の強化、欠員補充など)
この「なぜ採用するのか?」という目的が明確になっていなければ、採用戦略全体がぶれてしまいます。経営陣と人事部門が、この大前提をしっかりと共有することがスタートラインです。
採用ターゲット(ペルソナ)の明確化
次に、「どんな人が欲しいか」を具体的に定義します。ここで重要なのは、単なる「職務経歴書(スペック)」だけでなく、その人の価値観や志向性まで含めた「ペルソナ(人物像)」を描くことです。
まずは、そのポジションに必要なスキルや経験を整理します。
- 必須条件(Must):これがないと業務が遂行できない、最低限必要な条件。
- 歓迎条件(Want):必須ではないが、あれば尚良い条件。
ここで陥りがちなのが、必須条件を増やしすぎることです。条件を厳しくしすぎると、当然ながら対象者が減り、採用難易度が上がってしまいます。「本当にそれは必須か?」を問い直す視点が重要です。
ペルソナを明確にすることで、この後の「採用手法の選定」や「面接での見極め」の精度が格段に上がります。
採用手法(チャネル)の選定
ペルソナ(採用したい人物像)が明確になったら、そのペルソナが「どこにいるのか」「どの手法ならアプローチできるのか」を考え、採用手法(チャネル)を選定します。
世の中には多様な採用手法があります。代表的なものの特徴を理解し、組み合わせることが重要です。
| 手法 | メリット | デメリット |
| 求人広告(ナビサイト) | ・広範囲に告知できる ・多くの応募を集めやすい | ・採用単価が変動しやすい ・競合他社に埋もれやすい |
| 人材紹介(エージェント) | ・自社に合う人材を絞って紹介してもらえる ・採用工数を削減できる | ・採用決定時の費用が高額になりがち |
| ダイレクトリクルーティング | ・優秀な潜在層に直接アプローチできる ・自社の魅力を直接伝えられる | ・スカウト文面の作成など工数がかかる ・運用ノウハウが必要 |
| SNS採用 | ・企業の「素顔」やカルチャーを発信しやすい ・潜在層とフランクに繋がれる | ・炎上リスクがある ・継続的な発信が必要 |
| リファラル採用 | ・社員の紹介でミスマッチが少ない ・採用コストを大幅に削減できる | ・人間関係に依存しがち ・仕組み化しないと活性化しない |
| アルムナイ採用 | ・元社員の採用で即戦力性が高い ・カルチャーフィットの心配がない | ・退職者との関係性構築が必要 |
選考プロセスの設計と魅力付け(候補者体験)
採用手法が決まったら、応募者との具体的な接点である「選考プロセス」を設計します。
忘れてはならないのは、採用は企業が候補者を「見極める」場であると同時に、候補者に「選んでもらう」場でもある、という視点です。
- 面接の回数、各面接の担当者(人事、現場、役員など)を決めます。
- 各面接で「何を見極めるか」(スキル、カルチャーフィットなど)の評価基準を明確にし、面接官同士で目線を合わせます。
- 同時に、面接を「自社の魅力を伝える場(魅力付け)」として設計します。候補者の不安を解消し、入社意欲を高めるコミュニケーションが重要です。
迅速な連絡、丁寧なフィードバック、面接官の誠実な態度など、候補者が応募から内定までの一連のプロセスで感じる「候補者体験(CX=Candidate Experience)」を高めることが、内定辞退の防止に直結します。
効果測定と改善(PDCA)
採用戦略は、立てて終わりではありません。実行した結果を必ず振り返り、改善を続ける(PDCAサイクルを回す)ことが最も重要です。
戦略を立てる段階で、目標達成度を測るための指標(KGI/KPI)も設定しておきましょう。
- KGI(重要目標達成指標)の例
・目標採用人数、採用決定率(内定承諾率)、入社後定着率(1年後) - KPI(重要業績評価指標)の例
・応募数、書類通過率、面接通過率、採用単価(一人当たりコスト)
これらの数値を定期的に分析し、「どの採用手法からの応募者が、定着率が高いか」「選考プロセスのどこで辞退が多く発生しているか」といった課題を特定し、戦略の見直し(ステップ1〜4の改善)につなげていきます。
採用戦略を成功に導くための3つの重要ポイント
上記採用戦略の立て方5ステップに加えて、採用戦略の「質」を高め、成功に導くために意識していただきたい3つのポイントをご紹介します。
「採用広報」の視点を持つ(Employer Branding)
採用広報とは、「働く場所としての自社の魅力」を社外に発信し、認知度やブランドイメージを高める活動です。
求職者は、求人広告を見るだけでなく、必ずその会社のWebサイト、SNS、口コミサイトなどをチェックします。応募「前」の段階から、「この会社で働いてみたい」と思ってもらえるような情報発信(例:働く環境、社員のインタビュー、社内カルチャーが分かる記事など)を継続的に行うことが、応募の質と量を高める上で非常に有効です。
社内全体を巻き込む
採用は、人事部門だけの仕事ではありません。特に経営陣や、配属先となる現場社員の協力が不可欠です。
- 経営陣が自らの言葉で、会社のビジョンや求める人物像を発信する。
- 現場の面接官が、評価基準や候補者体験の重要性を理解し、魅力付けに協力する。
- 全社員が「自社の魅力を発信する広報担当」である意識を持つ。
人事が孤軍奮闘するのではなく、会社全体で採用に取り組む体制を作ることが、戦略成功の鍵となります。
新しい採用手法を恐れずに取り入れる
「昔からこの求人媒体を使っているから」「人材紹介が一番楽だから」
もし、従来の手法だけで採用に行き詰まりを感じているのであれば、勇気を持って新しい採用手法を戦略に組み込むことをお勧めします。特に「社内を巻き込む」ことにもつながる手法が、これからの採用戦略の軸となり得ます。
【関連】主な採用手法10選。おすすめの手法や採用成功の鍵を紹介
これからの採用戦略の切り札「リファラル採用」と「アルムナイ採用」の可能性
これからの採用戦略の「切り札」となる手法が、「リファラル採用」と「アルムナイ採用」です。
- リファラル採用:自社の社員に、知人や友人を紹介・推薦してもらう採用手法
- アルムナイ採用:一度退職した元社員(アルムナイ)を、再雇用する採用手法
これらが注目される理由は、多くの企業が抱える採用課題を根本から解決できる可能性を秘めているからです。
- 劇的な採用コストの削減
高額な求人広告費や人材紹介手数料がかかりません。紹介社員へのインセンティブや運用コストは発生しますが、従来の採用単価と比較して大幅なコストダウンが期待できます。 - 圧倒的なマッチング精度の高さ(ミスマッチ防止)
社員や元社員は、自社の良い面も課題も理解した上で、「この人なら自社で活躍できる」と判断して紹介してくれます。候補者側も、リアルな情報を得た上で入社を決めるため、入社後のギャップが少なく、定着率向上に直結します。 - 転職「潜在層」へのアプローチ
転職サイトには登録していない、今すぐの転職は考えていない「優秀な潜在層」にリーチできる唯一無二の手法です。
とはいえ、リファラル採用やアルムナイ採用を戦略的に進めるには、課題も伴います。
「社員がなかなか協力してくれない」「紹介が特定の社員に偏り、属人化してしまう」「誰が誰を紹介したか、管理が煩雑で把握できない」
これらの課題を解決し、採用戦略の一部として「仕組み化」するためには、専用ツールの活用が最も有効な手段です。
【関連】リファラル採用ツールおすすめ5選!メリットや選び方を徹底解説
おすすめのリファラル採用・アルムナイ採用を支援するサービス「リファアルム」

リファアルムは、リファラル採用とアルムナイ採用を同時に支援するサービスです。採用は感覚的に行うものではなく、全従業員を巻き込み、「全社一丸」となって取り組むことが大切です。「リファアルム」を使うことにより、従業員のリファラル採用やアルムナイ採用に対する「前向きな姿勢」を引き出すことが可能です。
1、従業員が「リファラル」「アルムナイ」に積極的に協力する、魅力的なカルチャーを形成できる。
2、創業以来のノウハウを活かし、「リファラル」「アルムナイ」だけではない採用活動全体の成功を支援。
3、協力してくれた従業員に対し、業界トップクラスのギフトラインナップで謝礼を提供。
リファラル採用・アルムナイ採用でお困りの企業様は、「リファアルム」にお問い合わせください
本記事では、採用戦略の重要性から具体的な立て方5ステップ、そして成功のポイントまでを解説してきました。
採用競争が激化する現代において、従来の手法だけに頼った場当たり的な「採用活動」では、優秀な人材を獲得し続けることは困難です。
自社の経営と連動した「採用戦略」を設計し、その戦略の「切り札」として、リファラル採用やアルムナイ採用といった、社内外の「つながり」を活用する新しい手法の導入をご検討ください。
しかし、「リファラル採用・アルムナイ採用について、専門家のアドバイスが欲しい」
「リファラル採用・アルムナイ採用を始めたいが、何から手を付けたら良いか分からない」
といったお悩みをお持ちの採用担当者様も多いのではないでしょうか。
そのようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ弊社の「リファアルム」にご相談ください。
ただツールを入れてもリファラル、アルムナイ採用が増えるとは限りません。
当社では経験豊富な採用コンサルタントが設計から運用までワンストップで支援します。
リファラル、アルムナイ採用成功のために必要なノウハウと実務支援、マネジメントをプロの人事チームが顧客の採用成功まで伴走します。
アルムナイ採用、そして採用活動全体でお困りのことがございましたら、まずはお気軽に下記よりお問い合わせください。
