アルムナイ採用の成功は「エンゲージメント」が鍵。退職後の関係構築の方法とメリットを解説
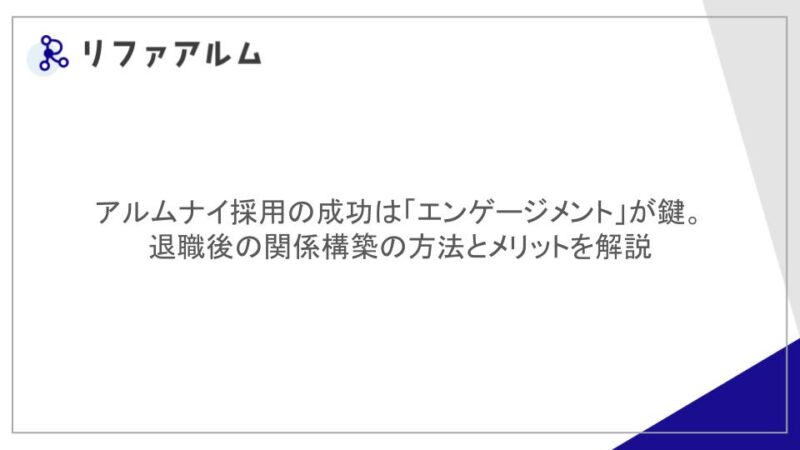
「求人を出しても募集が集まらない」 「採用しても、求める人材が辞退してしまう」 「採用活動に割くマンパワーが足りない」 「採用人数は変わらないのに、採用コストだけが増え続ける」
こうした様々な課題がある採用難の時代において、新たな解決策として注目を集めているのが「アルムナイ採用」です。
アルムナイ採用とは、企業の退職者=「アルムナイ」を、再び自社の貴重な人材として迎え入れる採用手法を指します。
しかし、ただ退職者に「戻ってこないか?」と声をかけるだけでは、アルムナイ採用は成功しません。成功の鍵は、退職した後も元従業員との良好な関係性、すなわち「エンゲージメント」を戦略的に維持・向上させることにあります。
本記事では、アルムナイ採用におけるエンゲージメントの重要性から、中小企業でも実践可能な具体的な関係構築のステップ、そして成功のための注意点までを徹底的に解説します。
もくじ
アルムナイ採用とは?
「アルムナイ(Alumni)」とは、ラテン語で「卒業生」や「同窓生」を意味する言葉です。ビジネスシーンでは、企業の「退職者」を指す言葉として使われています。
つまり「アルムナイ採用」とは、自社を退職した人材を再び雇用することです。
「いわゆる『出戻り社員』のことでは?」と思われるかもしれません。 従来の「出戻り」が、欠員補充などで場当たり的に行われることが多かったのに対し、「アルムナイ採用」は、退職者を企業の貴重な人材資産と捉え、戦略的に関係を構築し、再雇用につなげる「制度」であるという点で異なります。
【関連】なぜ今「出戻り採用」が注目されるのか?アルムナイ採用を導入すべき理由を解説
なぜ「アルムナイ採用」が注目されるのか
深刻な人手不足や採用コストの高騰は、大企業以上に中小企業の経営を圧迫します。アルムナイ採用は、こうした課題を解決する大きな可能性を秘めています。
- 即戦力としての期待
企業文化や業務プロセス、社内の人間関係をすでに理解しているため、入社後のオンボーディング(受け入れ研修)期間が短く、即戦力として活躍できます。 - 採用・教育コストの大幅な削減
求人広告費や人材紹介手数料といった外部コストがかかりません。また、ゼロから教育する必要がないため、教育コストも大幅に削減できます。 - ミスマッチの低減
企業側も本人側も、お互いの長所や短所、働き方を理解した上での再入社となるため、「こんなはずではなかった」という入社後のミスマッチが起こりにくいのが最大の強みです。 - 新しい知見や人脈の獲得
アルムナイが他社で経験した新しいスキル、知見、そして人脈を自社に持ち帰ってくれることも、大きなメリットと言えるでしょう。
特に中小企業や飲食業界では、一人の即戦力がもたらすインパクトは絶大です。だからこそ、アルムナイ採用が今、注目されているのです。
アルムナイ採用の成否を分ける「エンゲージメント」とは
本題である「アルムナイ採用におけるエンゲージメント」についてです。 なぜ、アルムナイ採用においてエンゲージメント(関係性の構築・維持)がそれほど重要なのでしょうか。
エンゲージメントが「低い」状態とは?
エンゲージメントが低い状態、それは「退職者とのつながりが完全に切れている状態」を指します。
- 退職した途端、一切の連絡が途絶えてしまう。
- 退職の経緯(辞め方)が悪く、会社に対してネガティブな印象を持っている。
- たまに会社から連絡が来ると思ったら「採用の勧誘」ばかりで、うんざりしている。
こうした状態では、いくら企業側が「戻ってきてほしい」と願っても、アルムナイの心には響きません。最悪の場合、連絡を無視されたり、企業の悪い評判を広められたりするリスクさえあります。
エンゲージメントが「高い」状態がもたらす3つのメリット
一方で、退職後も良好なエンゲージメントを維持できていると、企業にとって計り知れないメリットが生まれます。
- 再雇用のハードルが劇的に下がる
会社と継続的につながっていることで、アルムナイは会社の「今」を知っています。「最近、新しいサービスを始めたんだな」「あの時の同僚が活躍しているな」という情報が、復帰を検討する際の安心材料になります。会社への信頼感や愛着が残っているため、いざという時の再雇用のハードルが劇的に下がります。 - 採用チャネルとしての機能(リファラル採用)
ここが非常に重要なポイントです。高いエンゲージメントは、本人が復帰しなくても価値を生みます。 アルムナイが自社の「ファン」として、自身の友人・知人など、優秀な人材を紹介してくれる「リファラル採用」のハブとなってくれるのです。企業文化を理解したアルムナイからの紹介は、採用のミスマッチも起こりにくい、非常に質の高い採用チャネルとなります。 - 企業の「ファン」としての機能
アルムナイは、退職後も自社のサービスや商品の「優良顧客」や「ファン」であり続けてくれる可能性があります。特に飲食業などでは、元スタッフが常連客としてお店を応援してくれるケースも多いでしょう。SNSなどでポジティブな口コミを発信してくれる存在にもなり得ます。
このように、エンゲージメントを高めることは、単なる再雇用にとどまらない、多様な「採用資産」を築くことにつながるのです。
アルムナイ採用のエンゲージメントを高める4ステップ
「エンゲージメントの重要性は分かった。でも、大企業のような立派な仕組みは作れない…」 「ただでさえ人事が足りないのに、退職者のケアまで手が回らない」
そうお考えの担当者様も多いかと思います。アルムナイ採用のエンゲージメントは、小さな一歩から始められます。
退職時の体験(オフボーディング)を最重要視する
エンゲージメント構築は、退職が決まった瞬間から始まっています。 「立つ鳥跡を濁さず」といった一方的なものではなく、企業側がいかに「円満な退職」を演出し、将来のつながりを作れるか(オフボーディング)が最初の鍵です。
- 退職理由を真摯にヒアリングする(イグジットインタビュー)
「どうせ辞める人だから」と事務的に処理せず、なぜ退職を選ぶのか、会社への不満や改善点を真摯にヒアリングしましょう。この姿勢が、本人の会社への最終的な印象を決めます。 - 「いつでも戻ってこい」というポジティブなメッセージを伝える
「他社での経験はあなたの財産になる」「外で成長して、また一緒に働ける日を楽しみにしている」といったポジティブな言葉を、経営者や直属の上司から伝えることが非常に重要です。 - アルムナイ・ネットワーク(コミュニティ)への参加を打診する
「退職後も、会社の近況やお得な情報をお送りするコミュニティがあるのですが、参加しませんか?」と、このタイミングで次のステップ(ネットワーク)への参加を打診します。
アルムナイと連絡を取るためのツールを活用する
「まずスモールスタートをする」ことが重要です。
- Facebookの非公開グループ
コストをかけずに始められる代表的な方法です。クローズドな環境で情報交換ができます。 - 専用のメーリングリスト
退職時に同意を得たメールアドレスをリスト化し、BCCで一斉送信するだけでも立派なネットワークです。 - LINE公式アカウント
特に飲食業界や小売業界など、アルバイト・パートスタッフが多い企業と相性が良い方法です。クーポンや新メニュー情報を流す延長線上で、アルムナイとの接点を持てます。
重要なのは、このネットワークの「管理担当者」を(兼務でも良いので)決めることです。人事担当者、あるいは経営者自らがオーナーシップを持つことが成功の秘訣です。
【関連】アルムナイ採用を成功に導くツールとは?メリット・機能から導入の注意点まで解説
価値ある情報発信とコミュニケーション
ネットワークを作っても、発信する情報がなければ意味がありません。 ここで最大の注意点は、「採用募集の情報ばかり送らない」ことです。
関係構築が9割、募集が1割、くらいのバランスを心がけましょう。アルムナイにとって「価値がある」「懐かしい」と感じてもらえる情報発信がエンゲージメントを高めます。
■発信する内容の例
- 会社の近況
新サービス、新店舗オープン、業績、メディア掲載といったポジティブなニュース - 社内の様子
元同僚の活躍や社内イベントの様子(社内報の簡易版のようなもの) - 業界の最新情報
会社がキャッチした業界トレンドなど、アルムナイの現在の仕事にも役立つ情報 - アルムナイ限定の特典
飲食業なら限定割引クーポン、BtoB企業ならサービスの割引など - イベント告知
(ステップ4で後述する)交流会や勉強会の案内
【関連】アルムナイ採用成功の鍵は「コミュニケーション」にあり!退職後も関係を繋ぐ具体的な方法と実践ポイント
アルムナイ同士の「横のつながり」を促す
前述が「会社 対 アルムナイ(1:N)」の関係だとすれば、こちらは「アルムナイ同士(N:N)」の関係を作る、より発展的な段階です。
- オンライン/オフラインでの交流会(同窓会)を企画する
- アルムナイが講師となって、現役社員や他のアルムナイ向けに勉強会を開催してもらう
アルムナイ同士の横のつながりが生まれると、そこは「コミュニティ」へと進化します。会社が頻繁に情報発信しなくても、コミュニティ内でエンゲージメントが自然と維持・向上していく好循環が生まれます。
アルムナイにおけるエンゲージメント推進時の注意点と対策
アルムナイ採用におけるエンゲージメントはメリットばかりに見えますが、推進時には中小企業ならではの壁にぶつかることもあります。
マンパワー不足(「誰がやるのか?」問題)
最も多い課題です。「ただでさえ日々の採用業務で手一杯なのに…」という声が聞こえてきそうです。
- 完璧を目指さないこと。
まずは年数回のニュースレター(メルマガ)配信から始める、退職時のイグジットインタビューを丁寧に行うことを徹底するなど、できる範囲から始めましょう。 - 経営者が率先して発信する。
特に創業期や小規模な会社では、人事任せにせず、経営者自らがSNSグループなどで発信することが、アルムナイのエンゲージメントに最も強く響きます。
退職者=「裏切り者」という古い文化
「一度会社を辞めた人間を、なぜ優遇するのか」といった、現役社員からの反発や、経営陣の古い考え方が障害になるケースです。
- 経営陣の意識改革。
「終身雇用」が前提の時代は終わりました。「外で成長して戻ってくる」キャリアパスをポジティブなものとして捉える、という経営トップの明確な意思表示が不可欠です。 - 現役社員への配慮。
アルムナイを再雇用する際の処遇(給与、役職)や役割を明確にし、現役社員が不公平感を抱かないようなルール整備も同時に進める必要があります。
個人情報の取り扱い
退職者とはいえ、個人の連絡先を扱うことには細心の注意が必要です。
- 必ず「オプトイン(本人の同意)」を得る。
ステップ1の退職時に、ネットワークへの参加意思と、そのための連絡先利用について必ず本人の同意を得てください。 - 利用目的を明確にする。
「会社の近況やイベント情報の発信のために利用します」といった利用目的を明示し、いつでも配信停止(オプトアウト)できる導線を整えておきましょう。
【関連】アルムナイ採用の注意点7選!導入前に押さえるべきポイントを徹底解説
おすすめのアルムナイ採用を支援するサービス「リファアルム」

リファアルムは、リファラル採用とアルムナイ採用を同時に支援するサービスです。採用は感覚的に行うものではなく、全従業員を巻き込み、「全社一丸」となって取り組むことが大切です。「リファアルム」を使うことにより、従業員のリファラル採用やアルムナイ採用に対する「前向きな姿勢」を引き出すことが可能です。
1、従業員が「リファラル」「アルムナイ」に積極的に協力する、魅力的なカルチャーを形成できる。
2、創業以来のノウハウを活かし、「リファラル」「アルムナイ」だけではない採用活動全体の成功を支援。
3、協力してくれた従業員に対し、業界トップクラスのギフトラインナップで謝礼を提供。
アルムナイ採用でお困りの企業様は、「リファアルム」にお問い合わせください
採用難が続くこれからの時代、アルムナイ採用は、特にリソースの限られる中小企業にとって強力な採用戦略となります。
そして、その成功の鍵は、退職者を「過去の人」ではなく「未来のパートナー」として捉え、長期的な「エンゲージメント」を育むことに尽きます。
しかし、「アルムナイ採用について、専門家のアドバイスが欲しい」
「アルムナイ採用を始めたいが、何から手を付けたら良いか分からない」
といったお悩みをお持ちの採用担当者様も多いのではないでしょうか。
そのようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ弊社の「リファアルム」にご相談ください。
ただツールを入れてもリファラル、アルムナイ採用が増えるとは限りません。
当社では経験豊富な採用コンサルタントが設計から運用までワンストップで支援します。
リファラル、アルムナイ採用成功のために必要なノウハウと実務支援、マネジメントをプロの人事チームが顧客の採用成功まで伴走します。
アルムナイ採用、そして採用活動全体でお困りのことがございましたら、まずはお気軽に下記よりお問い合わせください。
