アルムナイ採用の「成功率」とは? 平均データや成功率を高める秘訣を解説
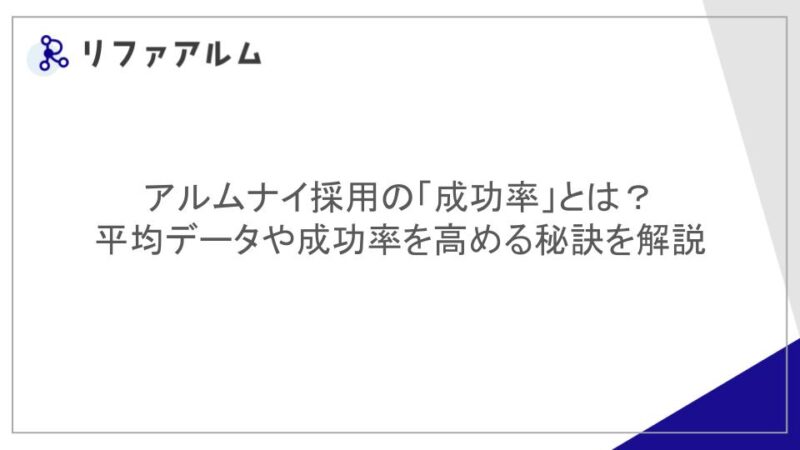
昨今、労働力人口の減少や採用手法の多様化に伴い、多くの企業が採用難に直面しています。特に、限られたリソースで優秀な人材を確保しなければならない企業にとって、採用活動は経営の根幹を揺るがす重要な課題です。
こうした背景の中、一度退職した元社員を再雇用する「アルムナイ採用(出戻り採用)」が、新たな採用戦略として注目を集めています。
アルムナイ採用を検討し始めたり、すでに導入している経営者様・人事担当者様の中には、 「アルムナイ採用の成功率って、実際のところどのくらいなんだろう?」 「他社はどのくらいの割合で再入社に至っているのか、目安が知りたい」 といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、なぜアルムナイ採用の合格率に明確なデータがないのか、その理由を解説するとともに、単なる「合格率」という数字に一喜一憂するのではなく、アルムナイ採用の「成功率(=採用決定率や定着率)」を高めるために本当に重要な、具体的な運用方法と秘訣を、企業の視点に立って分かりやすく解説します。
もくじ
アルムナイ採用の「成功率」に関する実態
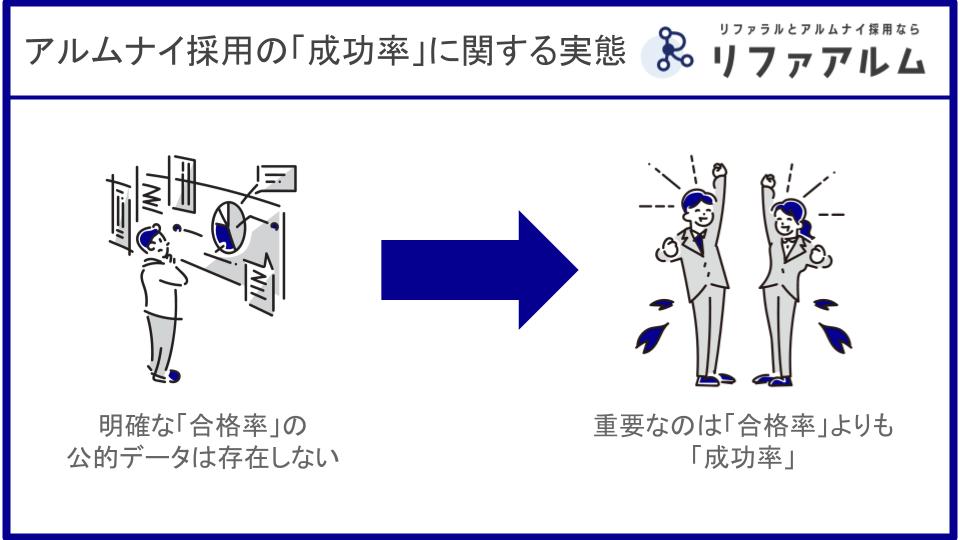
結論:明確な「合格率」の公的データは存在しない
まず、皆様が最も知りたいであろう「アルムナイ採用の合格率」についてですが、残念ながら、公的機関や大手調査会社が発表している信頼性の高い平均データは、2025年現在、ほぼ存在しません。
「合格率」と一口に言っても、それが「再応募の打診があったうち、内定を出した割合」なのか、「内定を出したうち、実際に入社(承諾)した割合」なのか、企業によって定義が曖昧です。
また、アルムナイ採用は、各企業の個別の事情(業界、企業規模、退職理由、再雇用の条件など)に大きく左右されるため、一般的な公募採用のように「平均〇〇%」といった統計データを出すこと自体が非常に難しいのです。
なぜ「合格率」という指標が生まれにくいのか?
アルムナイ採用で「合格率」という指標が生まれにくい最大の理由は、その採用プロセスが一般的な公募採用とは根本的に異なるためです。
通常の公募採用は、「不特定多数の応募者」を集め、「選考(書類選考・面接)」を経て、「内定」を出す、というフローが一般的です。そのため、「応募者数」を母数とした「内定率(合格率)」を算出しやすい構造になっています。
一方、アルムナイ採用は、
- 企業側から元社員に「戻ってこないか」と声をかける(スカウト)
- 元上司や同僚を介して「戻りたい」と相談がある(リファラル)
- 退職者ネットワークを通じて正式に応募がある
など、再入社に至るルートが多様です。 「応募」という明確なステップを踏まないケースも多く、「不特定多数の応募」対「選考」という構造になりにくいため、「合格率」を算出する前提条件そのものが当てはまりにくいのです。
重要なのは「合格率」よりも「成功率」
したがって、アルムナイ採用を成功させるためには、他社の「合格率」という曖昧な数字の目安を探すことよりも、自社が「アルムナイ(退職者)とどのような関係性を構築し、いかにスムーズな再入社につなげるか」というプロセス(仕組み)を設計・運用すること=「成功率」のほうが、はるかに重要です。
特に、経営者や人事と社員の距離が近い中小企業こそ、この「関係性」を活かした採用戦略を展開しやすいという強みがあります。
アルムナイ採用を導入する3つのメリット再確認

アルムナイ採用の成功率を高めるステップに進む前に、なぜ今アルムナイ採用が企業にとって有効なのか、そのメリットを改めて整理しておきましょう。皆様が抱える「採用費用が増え続ける」「求める人材が辞退してしまう」といった悩みを解決するヒントがここにあります。
採用コストと教育コストの大幅削減
アルムナイ採用が成功すれば、採用コストを劇的に削減できます。 公募に必要な求人広告費や、人材紹介会社に支払う高額な紹介手数料が発生しません。これは「採用費用が増え続ける」という悩みに対する直接的な解決策となります。
また、企業文化や基本的な業務内容をすでに理解しているため、入社後の教育コスト(研修時間や指導担当者の工数)も大幅に削減でき、即戦力としての活躍が期待できます。
【関連】アルムナイ採用のコストは安い?費用内訳と主要採用手法との比較を徹底解説
ミスマッチの低減と高い定着率
アルムナイ採用は、入社後のミスマッチを最小限に抑えられる点も大きなメリットです。 企業側は元社員の人柄や働きぶりを理解しており、アルムナイ側も社風や業務の実態を知った上で戻ることを決意しています。
お互いの理解があるため、「こんなはずじゃなかった」という入社後のギャップが起こりにくく、「求める人材が辞退してしまう」「せっかく採用したのにすぐに辞めてしまう」といった課題の改善につながり、結果として高い定着率が期待できます。
社内の活性化とエンゲージメント向上
アルムナイが他社で培った新しいスキル、知識、異なる視点を社内に持ち帰ることで、既存の業務プロセスや組織風土に良い刺激が与えられ、社内全体の活性化につながるケースも少なくありません。
また、「一度辞めた人が戻りたいと思う会社」であるという事実は、現職社員に対しても「自社は魅力的な職場である」というポジティブなメッセージとなり、エンゲージメント(会社への愛着や貢献意欲)の向上にも寄与します。
【関連】今、注目すべき「アルムナイ採用」5つのメリットと成功の秘訣
アルムナイ採用の「成功率」を高める5つの運用ステップ

では、ここからは本題である、アルムナイ採用の「成功率」を高めるための具体的な5つの運用ステップをご紹介します。採用のマンパワーが足りない企業でも実践できるよう、ポイントを絞って解説します。
アルムナイ採用に特化したツールで仕組みを作る
アルムナイ採用は、「退職した瞬間」から始まっています。 大前提として、社員が「円満退職」できるような風土づくりが不可欠です。アルムナイ採用に特化したツールを利用することで、情報管理が簡易的になり工数の削減にも繋がります。
その上で、退職後もアルムナイと継続的に接点を持てる「仕組み」を作りましょう。
- アルムナイ・ネットワークの構築
・退職者の同意を得た上で、連絡先(メールアドレスなど)を管理する名簿を作成する。 - 定期的な情報発信
・求人の作成やURLでの共有。
・会社の近況、新しい取り組み、求人情報などを定期的に発信する(例:アルムナイ向けニュースレターの配信)。
「マンパワーが足りない」場合は、こうしたツールやサービスを活用するのも一つの手です。
【関連】アルムナイ採用を成功に導くツールとは?メリット・機能から導入の注意点まで解説
アルムナイ採用の窓口(応募ルート)を明確にする
アルムナイが「古巣に戻りたい」と考えたときに、「誰に、どうやって連絡すればよいか」が分からない状態では、せっかくの機会を逃してしまいます。
- 専用窓口の設置
・自社の採用サイトやコーポレートサイトに「アルムナイ採用(カムバック採用)専用ページ」を設ける。
・人事担当者の専用連絡先(メールアドレスなど)を、退職時に伝えておく。 - カジュアルな相談ルートの確保
・元上司や同僚経由でも、気軽に相談できる雰囲気を作っておくことも有効です。
アルムナイがアクションを起こしやすいよう、窓口を明確にし、その存在を(ステップ1の仕組みを通じて)周知しておくことが重要です。
公正な「再選考プロセス」を設計する
アルムナイ採用の成功において、このステップが最も重要と言っても過言ではありません。 「元社員だから」という理由だけで、面接もなしに無条件で再入社させるのは非常に危険です。これは、後々のミスマッチや、現職社員の不満につながる可能性があります。
アルムナイ採用であっても、必ず「公正な選考プロセス」を設計し、運用してください。
- 退職理由の確認
・なぜ退職したのか。もし人間関係や待遇などのネガティブな理由だった場合、その原因は現在解消されているか。 - 他社での経験と成長
・退職後、他社でどのような経験を積み、何を学び、どう成長したか。そのスキルが自社でどう活かせるか。 - 再入社への期待と本人の希望のマッチング
・会社側がアルムナイに期待する役割(ポジション)と、本人が希望する働き方やキャリアプランが一致しているか。
在籍時とは異なる「現在のスキルや経験」を客観的に評価する基準を設け、現職社員との公平性を保つことが、円満な再入社と定着の鍵となります。
処遇(給与・役職)の決め方を整備する
選考プロセスと並んでトラブルになりやすいのが、処遇(給与や役職)の決定です。 「在籍時の給与をスライドさせる」「他社での給与をそのまま適用する」といった安易な決め方は避けましょう。
以下の3つのバランスを考慮して、総合的に決定する必要があります。
- 在籍時の処遇(当時の評価や役職)
- 他社での経験・スキル(ステップ3の選考で評価した内容)
- 現職社員との公平性(同年代や同等のスキルを持つ社員の処遇とのバランス)
特に「3. 現職社員との公平性」は重要です。アルムナイを優遇しすぎると、長く会社に貢献してくれている社員のモチベーションを著しく低下させる恐れがあります。選考プロセスと同様に、処遇の決定ロジックを明確にしておくことが求められます。
【関連】アルムナイ採用の待遇はどう決める?適切な決め方と注意点を解説
受け入れ体制の整備とオンボーディング
無事に再入社が決まった後も油断は禁物です。 「元社員だから大丈夫だろう」と放置せず、改めて「オンボーディング(受け入れ・定着支援)」のプロセスを実施してください。
本人が知らない間に、社内のルール、システム、組織体制、人間関係は変化しているものです。
- 変更点(ルール、システムなど)のインプット
- 新しい部署のメンバーとの顔合わせ、コミュニケーションの場の設定
- 再入社後の定期的なフォロー面談(例:1ヶ月後、3ヶ月後)
「浦島太郎」状態にさせないよう、会社側が丁寧に関与し、スムーズな立ち上がりをサポートすることで、アルムナイの早期活躍と定着につながります。
アルムナイ採用で「成功率」を下げる3つの注意点
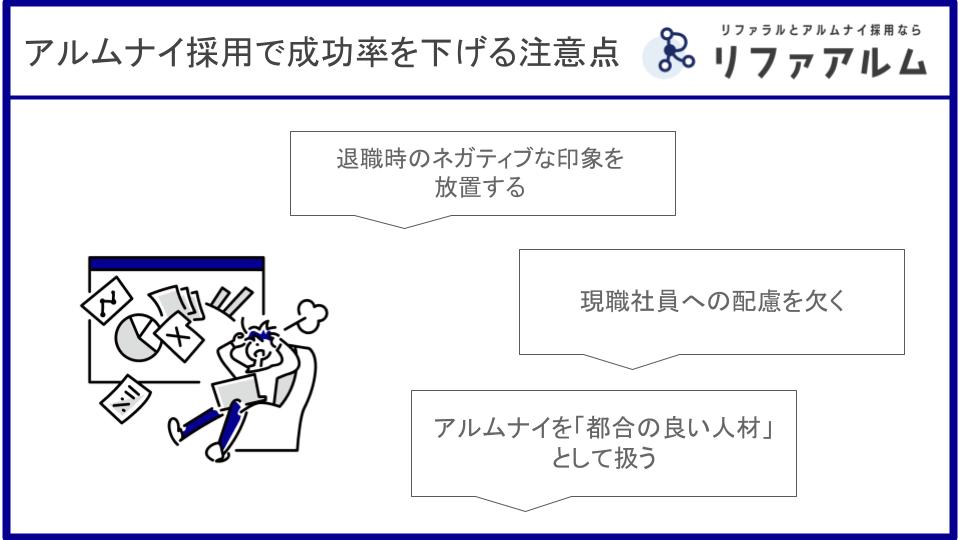
最後に、アルムナイ採用の成功率を下げる(=応募がない、再入社しても定着しない)ケースに共通する注意点を3つご紹介します。
退職時のネガティブな印象を放置する
アルムナイ採用は、社員が「円満退職」できることが大前提です。 退職交渉がこじれたり、上司が高圧的な態度を取ったり、必要な手続きが杜撰だったりすると、「二度とあの会社には戻りたくない」というネガティブな印象を与えてしまいます。
退職者が「この会社で働けてよかった」と感じられるような、丁寧な退職プロセス(オフボーディング)を徹底することが、未来のアルムナイ採用成功への第一歩です。
現職社員への配慮を欠く
アルムナイの再入社は、現職社員にとって複雑な感情を生む可能性があります。 「一度辞めた人を優遇するのはズルい」 「なぜあの人が自分より高い給与で戻ってくるのか」 といった不公平感が蔓延すると、組織全体の士気が下がってしまいます。
アルムナイ採用を行う目的(なぜ会社にとってプラスなのか)、選考基準(ステップ3)、処遇の考え方(ステップ4)などを、現職社員にも可能な範囲で説明し、理解と納得感を得る努力が不可欠です。
アルムナイを「都合の良い人材」として扱う
「急に人手が足りなくなったから、誰でもいいから戻ってきてほしい」 「元社員だから、無理な条件でも働いてくれるだろう」 といった、会社側の都合だけを押し付けるような姿勢は、必ず失敗します。
アルムナイは、他社での経験を積んだ「貴重な外部人材」であり、「対等なパートナー」として尊重する姿勢が求められます。選考プロセスを通じて、本人のキャリアプランや希望に真摯に耳を傾け、お互いがWin-Winとなる条件を模索することが重要です。
おすすめのアルムナイ採用を支援するサービス「リファアルム」

リファアルムは、リファラル採用とアルムナイ採用を同時に支援するサービスです。採用は感覚的に行うものではなく、全従業員を巻き込み、「全社一丸」となって取り組むことが大切です。「リファアルム」を使うことにより、従業員のリファラル採用やアルムナイ採用に対する「前向きな姿勢」を引き出すことが可能です。
1、従業員が「リファラル」「アルムナイ」に積極的に協力する、魅力的なカルチャーを形成できる。
2、創業以来のノウハウを活かし、「リファラル」「アルムナイ」だけではない採用活動全体の成功を支援。
3、協力してくれた従業員に対し、業界トップクラスのギフトラインナップで謝礼を提供。
アルムナイ採用でお困りの企業様は、「リファアルム」にお問い合わせください
本記事では、アルムナイ採用の「成功率」について、その実態と成功の秘訣を解説してきました。
アルムナイ採用の「合格率」には、公募採用のような明確な平均データはありません。
重要なのは、他社の数値を追い求めることではなく、自社がアルムナイ(退職者)と良好な関係性を構築し、再入社を歓迎する「仕組み」を整え「成功率」を上げることです。
ご紹介した運用ステップを実践することで、アルムナイ採用の「成功率」は着実に高まっていくはずです。
しかし、「アルムナイ採用について、専門家のアドバイスが欲しい」
「アルムナイ採用を始めたいが、何から手を付けたら良いか分からない」
といったお悩みをお持ちの採用担当者様も多いのではないでしょうか。
そのようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ弊社の「リファアルム」にご相談ください。
ただツールを入れてもリファラル、アルムナイ採用が増えるとは限りません。
当社では経験豊富な採用コンサルタントが設計から運用までワンストップで支援します。
リファラル、アルムナイ採用成功のために必要なノウハウと実務支援、マネジメントをプロの人事チームが顧客の採用成功まで伴走します。
アルムナイ採用、そして採用活動全体でお困りのことがございましたら、まずはお気軽に下記よりお問い合わせください。
