アルムナイ採用の成功は「関係構築」が9割!退職後もつながりを保つ方法と注意点とは
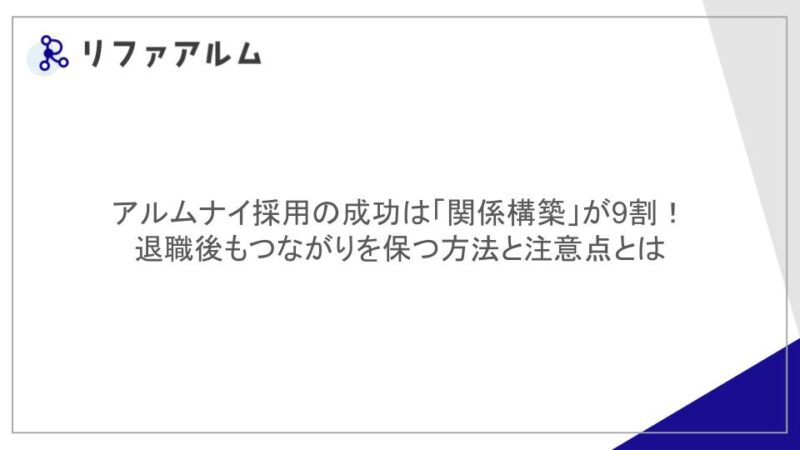
採用活動の難易度が年々高まる中、新たな採用手法として「アルムナイ採用」が注目されています。アルムナイ(Alumni)とは「卒業生」を意味し、一度自社を退職した人材を再び雇用する「出戻り採用」のことを指します。
即戦力としての活躍や、採用・教育コストの削減が期待できるため、多くの企業が関心を寄せています。
しかし、「カムバック制度を作ったものの、応募がまったくない」「退職者とどう連絡を取ればいいか分からない」といった課題を抱えている人事担当者様も多いのではないでしょうか。
アルムナイ採用を成功させる鍵は、制度を作ること以上に、退職者との継続的な「関係構築」にあります。
本記事では、アルムナイ採用を成功に導くための関係構築の重要性から失敗しないための注意点まで、分かりやすく解説します。
もくじ
アルムナイ採用とは?
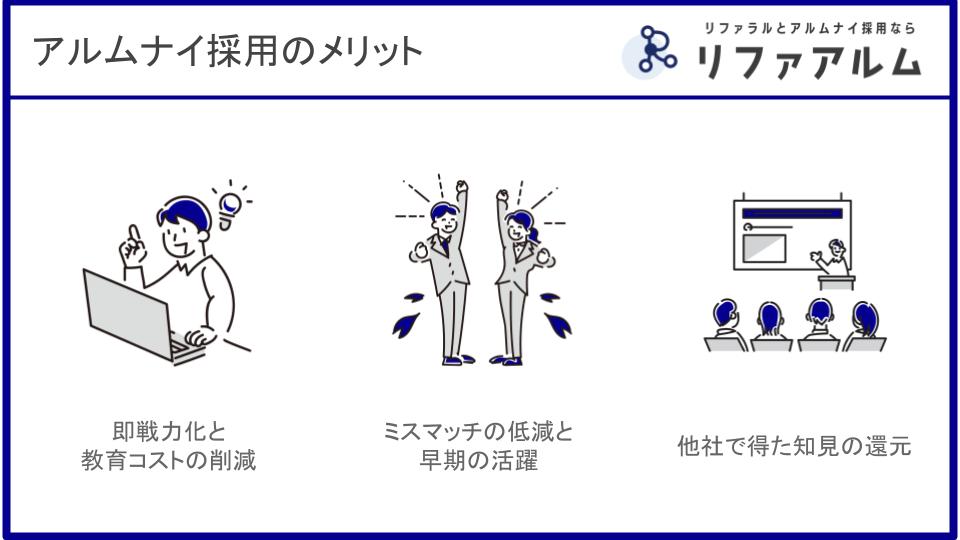
まずは、アルムナイ採用の基本的なメリットと、なぜ「関係構築」がこれほどまでに重要視されるのか、その背景から見ていきましょう。
アルムナイ採用のメリット
アルムナイ採用には、通常のキャリア採用にはない大きなメリットがあります。
- 即戦力化と教育コストの削減
企業文化や業務内容をすでに理解しているため、入社後のオンボーディング(受け入れ研修)がスムーズです。即戦力として短期間で活躍してもらえる可能性が高く、教育コストも大幅に削減できます。 - ミスマッチの低減と早期の活躍
「思っていた会社と違った」というカルチャーフィットのミスマッチが起こりにくいのが特長です。お互いの強みも弱みも理解した上での再入社となるため、早期からパフォーマンスを発揮しやすくなります。 - 他社で得た知見の還元
退職後に他社で培った新しいスキル、知識、人脈を自社に持ち帰ってもらえる可能性があります。これは既存社員にとっても良い刺激となり、組織の活性化につながります。
【関連】今、注目すべき「アルムナイ採用」5つのメリットと成功の秘訣
なぜ退職者との「関係構築」がアルムナイ採用の成否を分けるのか
これだけのメリットがあるにもかかわらず、多くの企業がアルムナイ採用に苦戦しているのはなぜでしょうか。それは、退職者との「関係」が途切れてしまっているからです。
- 「転職」が当たり前の時代に
終身雇用が当たり前ではなくなり、キャリアアップやライフスタイルの変化のために転職することは、もはやネガティブなことではありません。退職は「裏切り」ではなく、あくまで個人の「キャリア選択」の一つです。 企業側もこの変化を受け入れ、退職者を「一度辞めた人」ではなく、「外の世界を経験した貴重な人材」と捉え直す必要があります。 - 「戻りたい」と思っても、声を上げにくい
退職者側にも、「戻りたい」という気持ちが芽生えることがあります。 「他社を経験して、改めて前の会社の良さが分かった」 「育児が落ち着いたら、またあの環境で働きたい」 しかし、「自分から『戻りたい』と言うのは気まずい」「会社にどう思われるか不安」といった心理的なハードルが存在します。
このハードルを下げ、いつでも戻ってこられる雰囲気を作ることが、企業側に求められる「関係構築」の役割です。 - 「円満退職」が関係構築のスタートライン
アルムナイ採用に向けた関係構築は、採用選考の時点から始まっていますが、最も重要なのは「退職時」の対応です。 不満を抱えたまま退職したり、引き継ぎでトラブルになったりすれば、その後の良好な関係は望めません。退職の意向を受け止めた瞬間から、次のキャリアを応援し、感謝を伝えて送り出す「円満退職」こそが、関係構築の絶対的なスタートラインとなります。
アルムナイ採用における退職者との関係構築は「いつ」から「どう」始めるべきか
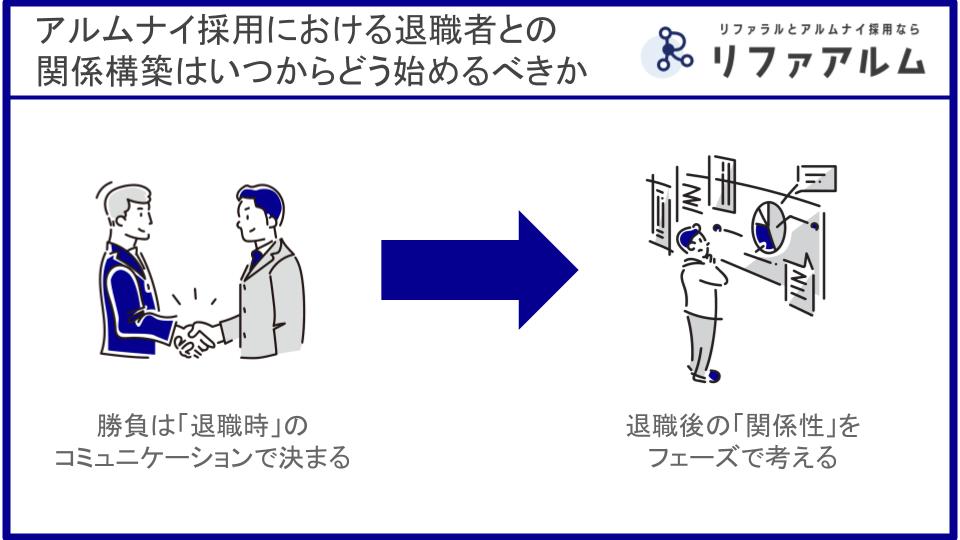
アルムナイ採用の退職者との関係構築において良好な関係を築くには、タイミングと方法が重要です。ここでは具体的なステップを時系列で解説します。
勝負は「退職時」のコミュニケーションで決まる
退職者との関係構築の成否は、退職時の対応で9割決まると言っても過言ではありません。
- 退職理由の丁寧なヒアリング
退職の意向を受けたら、まずは退職面談(イグジットインタビュー)の場を設けましょう。重要なのは、退職理由を表面的なものではなく、本音ベースで深くヒアリングすることです。「給与が不満」「人間関係が」といったネガティブな理由が出てきても、否定せずに真摯に受け止め、会社の課題として向き合う姿勢を見せることが信頼につながります。 - これまでの貢献への感謝と、ポジティブな送り出し
最終出社日やその前後には、上司や人事から、これまでの会社への貢献に対する感謝を具体的に伝えます。「外の世界で頑張ってほしい」「今回の決断を応援している」というポジティブなメッセージで送り出しましょう。 - 「いつでも戻ってきてほしい」という意思表示と、連絡先交換の許可取り
最後に、「もし将来、また縁があったら、いつでも戻ってきてほしい」「会社の近況なども時々知らせたいので、連絡先(個人メールやSNSなど)を交換しても良いか?」と明確に意思を伝えます。この一言が、退職者の心理的ハードルを大きく下げます。
退職後の「関係性」をフェーズで考える
退職後も、継続的な接点を持つことが重要です。ただし、頻度や内容は相手の状況に合わせて変える必要があります。
- フェーズ1:退職直後(~1ヶ月)
まずは無事に退職手続きが完了したことの連絡や、「新しい職場はどうですか?」といった簡単な近況伺いを、元上司や人事から個人宛に送ると丁寧です。 - フェーズ2:定着期(3ヶ月~半年)
新しい職場にも慣れてきた頃です。会社の近況を伝えるニュースレターを送ったり、「近くに来たのでランチでもどう?」とカジュアルに誘ったりするのに適した時期です。 - フェーズ3:長期(1年~)
ここからは「ゆるく、長く」つながる関係を目指します。定期的な情報提供を続けつつ、相手のキャリアの節目(昇進など)でお祝いのメッセージを送るなど、相手を「忘れていない」というシグナルを送り続けます。
アルムナイ採用における退職者との関係構築の方法6選

「アルムナイ採用において退職者との関係構築が重要なのは分かったが、かけられるコストもマンパワーも少ない」という企業やご担当者様も多いのではないでしょうか。 ここでは、できるだけコストを抑えて開始できる6つの方法をご紹介します。
アルムナイ・データベースの整備
まずは、退職者の情報を一元管理するデータベース(台帳)を作成しましょう。
- 管理すべき項目例
・氏名、在籍時の部署・役職、退職日
・個人の連絡先(メールアドレス、電話番号、SNSアカウントなど ※許可を得たもの)
・退職理由(ヒアリング内容)
・現在の勤務先(把握していれば)
・連絡履歴(いつ、誰が、どんな内容で連絡したか)
※個人情報の取り扱いになるため、利用目的(アルムナイ採用や情報提供のため)を明確にし、アクセス権限を絞るなど、セキュリティ管理は徹底してください。
定期的なニュースレターの配信
四半期に1回、半年に1回程度の頻度で、アルムナイ向けのニュースレターを配信するのも効果的です。
- 配信内容の例
・会社の近況(新店舗オープン、新サービス開始、業績の概要など)
・社内イベントの様子
・現役社員の活躍紹介
・アルムナイの活躍紹介(許可を得て掲載)
ポイントは、「求人情報」ばかりを送って売り込み感を出すのではなく、「会社のファンでいてもらう」ための手紙のようなトーンを意識することです。
SNS(Facebookグループ、LINE)の活用
よりカジュアルなコミュニケーションには、SNSが有効です。アルムナイ限定のグループや、オープンチャットなどを作成し、参加を呼びかけます。 現役社員も一部参加し、社内の様子を写真付きで投稿したり、アルムナイ同士が情報交換できる「コミュニティ」として機能させることが理想です。
【関連】アルムナイ採用を成功させるコミュニティの作り方と運営のコツ
アルムナイ限定イベントの開催
年に1回程度、アルムナイを招待するイベントを開催するのも良いでしょう。 堅苦しいものではなく、オフィスでの簡単な懇親会や、オンラインでの近況報告会など、小規模なもので構いません。 「特別に招待されている」という意識が、会社への帰属意識を再び芽生えさせます。
元上司や人事からの個別コンタクト
最も効果的なのは、やはり「個人」としてのつながりです。 会社からの形式的な連絡だけでなく、元上司や人事担当者が「個人」として、誕生日のお祝いメッセージを送ったり、SNSで活躍ぶりを見て「いいね!」を押したりするだけでも、つながりは維持できます。「会社」としてではなく「人」としての関係が、いざという時の信頼につながります。
アルムナイ採用に特化したツールの活用
上記で紹介したデータベースの整備やニュースレターの配信、コンタクトを取る際の手軽さなどは、アルムナイ採用に特化したツールを導入することでより活用が簡易的になります。
アルムナイとの関係構築(コミュニケーション)を円滑化し、情報管理も行えることで、アルムナイ採用を成功へと導くことができます。
【関連】アルムナイ採用を成功に導くツールとは?メリット・機能から導入の注意点まで解説
アルムナイ採用の退職者との関係構築で失敗しないための注意点

アルムナイ採用の退職者との関係構築は、一歩間違えると「しつこい」「プライバシーの侵害だ」と受け取られかねません。以下の点に注意し、細心の配慮を持って進めましょう。
連絡の頻度としつこさの境界線
連絡の頻度は最も注意すべき点です。良かれと思って送った連絡が、相手にとっては負担になることもあります。 ニュースレターは四半期に1回程度、個別連絡も半年に1回程度を目安にし、相手からの返信を強要しないことが鉄則です。「連絡が不要な場合は、いつでも配信停止できます」といった一文を添える配慮も重要です。
ネガティブな理由での退職者への対応
人間関係のトラブルや、会社の体制への強い不満を持って辞めた方に対して、無理に関係を構築しようとするのは逆効果です。 まずは退職時のヒアリングで、会社側の非を認め、謝罪すべき点は誠実に謝罪することが先決です。関係構築は、その「わだかまり」が解消されてから、慎重に始めるべきです。
「再入社」をゴールにしすぎない
関係構築の目的は、あくまで「退職者と良好な関係を保ち、会社のファンでいてもらうこと」です。再入社はその結果の一つに過ぎません。 「いつ戻ってくるの?」と再入社をゴールにしすぎると、相手はプレッシャーを感じて離れていってしまいます。たとえ再入社につながらなくても、良き理解者としてリファラル(知人・友人の紹介)につながったり、取引先として協業したりする可能性も秘めています。
再入社時の処遇の透明性
いざ「戻りたい」という声があった際に、処遇(給与、役職など)で揉めないよう、ルールを明文化しておくことが望ましいです。 「カムバック制度」として、「在籍時の評価をどう反映するか」「他社での経験年数をどう加味するか」などを事前に定めておくことで、スムーズな受け入れが可能になります。
おすすめのアルムナイ採用を支援するサービス「リファアルム」

リファアルムは、リファラル採用とアルムナイ採用を同時に支援するサービスです。採用は感覚的に行うものではなく、全従業員を巻き込み、「全社一丸」となって取り組むことが大切です。「リファアルム」を使うことにより、従業員のリファラル採用やアルムナイ採用に対する「前向きな姿勢」を引き出すことが可能です。
1、従業員が「リファラル」「アルムナイ」に積極的に協力する、魅力的なカルチャーを形成できる。
2、創業以来のノウハウを活かし、「リファラル」「アルムナイ」だけではない採用活動全体の成功を支援。
3、協力してくれた従業員に対し、業界トップクラスのギフトラインナップで謝礼を提供。
アルムナイ採用でお困りの企業様は、「リファアルム」にお問い合わせください
本記事では、アルムナイ採用の関係構築について、具体的な方法や成功のための注意点まで網羅的に解説しました。
アルムナイ採用の成功は、制度の有無ではなく、日頃からの地道な「関係構築」にかかっています。
しかし、「アルムナイ採用について、専門家のアドバイスが欲しい」
「アルムナイ採用を始めたいが、何から手を付けたら良いか分からない」
といったお悩みをお持ちの採用担当者様も多いのではないでしょうか。
そのようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ弊社の「リファアルム」にご相談ください。
ただツールを入れてもリファラル、アルムナイ採用が増えるとは限りません。
当社では経験豊富な採用コンサルタントが設計から運用までワンストップで支援します。
リファラル、アルムナイ採用成功のために必要なノウハウと実務支援、マネジメントをプロの人事チームが顧客の採用成功まで伴走します。
アルムナイ採用、そして採用活動全体でお困りのことがございましたら、まずはお気軽に下記よりお問い合わせください。
