アルムナイ採用の制度設計はどう進める?具体的な手順と成功に導く3つのポイント
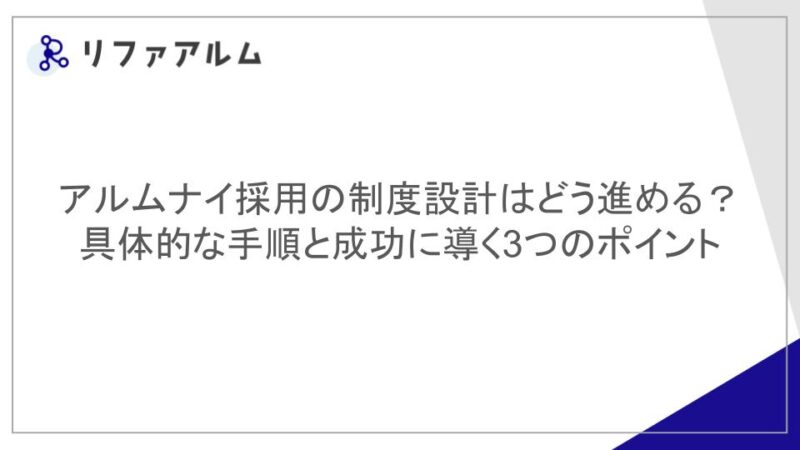
「即戦力となる人材を採用したいが、なかなか良い出会いがない…」 「採用コストは増える一方なのに、ミスマッチが起きてしまう…」
こうした悩みを抱える中小企業の経営者・人事担当者の間で今、「アルムナイ採用」が新たな人材戦略として注目を集めています。
アルムナイ採用とは、一度自社を退職した人材を再び雇用する採用手法のこと。企業の文化や事業内容を深く理解しているため、即戦力としての活躍が期待でき、採用コストの削減にも繋がる可能性があります。
しかし、「アルムナイ採用に注目しているが、いざ導入しようとすると『どんな制度を作ればいいのか?』『何から手をつければいいのか分からない』」と、具体的な制度設計の段階で足踏みしてしまうケースも少なくありません。
そこで本記事では、アルムナイ採用の制度設計における具体的なステップから、成功のためのポイント、そして就業規則への記載例まで、担当者が本当に知りたい情報を網羅的に解説します。
もくじ
アルムナイ採用とは?
「アルムナイ(Alumni)」とは、もともとラテン語で「卒業生」や「同窓生」を意味する言葉です。ここから転じて、ビジネスの世界では企業の退職者を指す言葉として使われています。
つまり、アルムナイ採用とは、企業の「卒業生」である退職者を、再び社員として迎え入れる採用手法を指します。
カムバック採用との違い
アルムナイ採用と似た言葉に「カムバック採用」があります。両者に厳密な定義の違いはありませんが、一般的に以下のような使い分けがされる傾向にあります。
- カムバック採用
結婚・出産・介護といったやむを得ない理由で退職した社員を対象とすることが多い。 - アルムナイ採用
スキルアップのための転職や起業など、ポジティブな理由も含め、あらゆる退職者を対象とする、より広義な概念。
近年では、退職理由を問わず、退職者との繋がりを企業の資産と捉えるアルムナイ採用の考え方が主流になりつつあります。
【関連】アルムナイ採用とカムバック採用の違いとは?メリットから導入ステップまで解説
なぜ今、アルムナイ採用が重要視されるのか?
アルムナイ採用が注目される背景には、現代の日本が抱える社会的な課題があります。
- 労働人口の減少と採用競争の激化
少子高齢化に伴い、企業の採用活動は年々難しくなっています。特に専門的なスキルを持つ人材の獲得競争は激しく、中小企業にとっては大きな課題です。 - 多様な働き方の浸透
転職が当たり前になり、一つの企業に勤め上げるという価値観は変化しました。優秀な人材ほど、自身のキャリアアップのために新たな環境を求める傾向にあります。 - 外部で得た新たな知識やスキルの還元への期待
退職者が他社や異業種で得た新しい知識、スキル、人脈は、企業にとって大きな財産です。彼らが戻ってくることで、組織に新たな風を吹き込み、イノベーションを促進する効果が期待されています。
こうした背景から、退職者を「裏切り者」ではなく「一度は自社で共に働いた貴重な人材」と捉え、再び協働する可能性を模索するアルムナイ採用が、合理的な人材戦略として重要視されているのです。
アルムナイ採用の制度設計において知っておきたいメリットとデメリット
アルムナイ採用は魅力的な手法ですが、もちろん良い面ばかりではありません。制度設計を始める前に、メリットとデメリットを正しく理解し、自社にとって本当に有効な手段かを見極めましょう。
アルムナイ採用のメリット
- 即戦力の確保とミスマッチの防止
最大のメリットは、即戦力となる人材を確保できる点です。自社の事業内容や企業文化、人間関係を既に理解しているため、入社後の立ち上がりが非常にスムーズです。また、お互いのことをよく知っているため、「期待していた人物像と違った」という採用のミスマッチを大幅に減らすことができます。 - 採用・教育コストの削減
アルムナイは、求人広告や人材紹介会社を介さずに直接アプローチできるケースが多く、採用コストを大幅に削減できます。また、基本的な業務内容や社内ルールを理解しているため、新人研修のような大掛かりな教育コストも不要です。 - 多様な知見による組織の活性化
アルムナイが他社で培った新しいスキルやノウハウ、異なる視点や価値観を持ち帰ることで、組織に良い化学反応が生まれます。既存のやり方にとらわれない新しいアイデアが生まれ、事業の成長やイノベーションのきっかけになることも少なくありません。 - 企業文化の維持・強化とエンゲージメント向上
アルムナイが再び自社を選んでくれることは、既存社員にとって「外の世界を知った上で、それでも戻りたいと思える魅力的な会社なんだ」というポジティブなメッセージになります。これにより、社員のエンゲージメント(会社への愛着や貢献意欲)向上にも繋がります。
【関連】今、注目すべき「アルムナイ採用」5つのメリットと成功の秘訣
アルムナイ採用のデメリット
- 既存社員との軋轢を生む可能性
特に退職前より良い待遇や役職で復帰した場合、既存社員から「なぜ一度辞めた人が優遇されるのか」といった不満の声が上がる可能性があります。既存社員への丁寧な説明と、公平性の高い制度設計が不可欠です。 - 待遇・役職の調整が難しい
退職後の経験やスキルをどう評価し、給与や役職に反映させるかは非常に難しい問題です。在籍時の給与をベースにするのか、現在の市場価値で判断するのか、明確な基準がないとトラブルの原因になります。 - 必ずしも良い関係で再入社するとは限らない
退職の理由や経緯によっては、復帰後に再び同じような課題に直面し、早期離職に繋がるケースも考えられます。退職時の状況や、復帰を希望する理由については、慎重に確認する必要があります。
【関連】アルムナイ採用の導入前に知っておくべきデメリットとは?具体的な対策と成功に導くポイントを解説
アルムナイ採用の制度設計を始める前の準備
メリット・デメリットを理解した上で、いよいよアルムナイ採用の制度設計に入ります。しかし、いきなり規程を作り始めるのは禁物です。その前に、制度の土台となる「思想」を固める準備段階が極めて重要です。
1.目的の明確化「なぜアルムナイ採用を行うのか?」
まずは、自社がアルムナイ採用を導入する目的をはっきりとさせましょう。目的によって、制度の内容や対象者も変わってきます。
- 欠員補充
→即戦力性を重視。退職前のパフォーマンス評価を基準にする。 - 新規事業の推進
→外部での経験やスキルを重視。退職後のキャリアを高く評価する。 - 組織の多様性確保
→幅広い退職者を対象とし、柔軟な働き方を認める。
「なぜ、アルムナイ採用なのか?」この問いに明確に答えられるようにしておくことが、ブレない制度を作る第一歩です。
2.対象者の定義「誰をアルムナイとみなすか?」
次に、制度の対象となる「アルムナイ」の範囲を定義します。対象者を広げすぎると管理が煩雑になり、狭すぎると制度が形骸化してしまいます。
<定義の検討項目例>
- 勤続年数
「勤続3年以上の者」など - 役職
制限を設けるか、設けないか - 退職理由
自己都合退職のみか、懲戒解雇などを除く全ての退職者を対象とするか - 退職後の経過年数
「退職後5年以内の者」など
これらの項目を組み合わせ、自社の目的に合った対象者像を具体的にしましょう。
3.退職者との関係構築(アルムナイ・ネットワーク)
どんなに素晴らしい制度を作っても、肝心の退職者と繋がっていなければ意味がありません。制度設計と並行して、退職者との継続的な接点を持つための仕組み(アルムナイ・ネットワーク)を構築しましょう。
<ネットワーク構築の具体例>
- 退職者専用のSNSグループ(Facebook、LinkedInなど)の作成
- メーリングリストによる近況報告やイベント案内の配信
- 定期的な交流会やセミナーの開催
重要なのは、一方的な情報発信ではなく、双方向のコミュニケーションを意識することです。「いつでも戻ってこれる場所」という安心感を育むことが、将来の再入社に繋がります。
アルムナイ採用における制度設計の具体的な5つのステップ
準備が整ったら、いよいよ制度の具体的な中身を作っていきます。ここでは、アルムナイ採用の制度設計のプロセスを5つのステップに分けて解説します。
採用基準の策定
「誰を」「どのような基準で」再雇用するのかを明確にします。基準が曖昧だと、既存社員から不公平感を持たれたり、場当たり的な運用になったりする原因となります。
<採用基準の検討項目>
- スキル・経験
在籍時のスキルに加え、退職後に得たスキルをどう評価するか - パフォーマンス
在籍時の人事評価や実績を参考にするか - カルチャーフィット
会社の理念や価値観に再び共感できるか - 復帰理由
なぜ再び自社で働きたいのか、その動機はポジティブなものか
これらの基準を言語化し、社内で共有しておくことが重要です。
待遇・条件の決定
アルムナイ採用で最もデリケートな部分が、給与や役職といった労働条件です。既存社員との公平性を保ちつつ、アルムナイ本人も納得できる条件を設定する必要があります。
<待遇・条件の決定パターン>
- A) 在籍時を基準とする
在籍時の役職・給与をベースに、勤続年数などを考慮して再設定する。 - B) 現在のスキル・市場価値で再評価する
通常の中途採用と同様に、現在のスキルや経験を評価してゼロベースで決定する。 - C) AとBのハイブリッド
在籍時の待遇を最低保証としつつ、退職後のキャリアを上乗せ評価する。
どのパターンを選ぶにせよ、「なぜこの待遇なのか」を論理的に説明できる明確な根拠を用意しておくことが不可欠です。
【関連】アルムナイ採用を成功させる条件とは?制度設計から待遇の決定まで解説
選考プロセスの設計
元社員だからといって、無条件で採用するのは望ましくありません。お互いの現状を理解し、ミスマッチを防ぐためにも、適切な選考プロセスを設計しましょう。
<選考プロセスの検討項目>
- 応募方法
専用の窓口を設けるか、通常の中途採用と同じ窓口で受け付けるか。 - 選考フロー
書類選考や面接の回数をどうするか。一次面接を免除するなどの配慮も考えられます。 - 面接官
人事担当者に加え、当時の上司や同僚、経営層など、多角的な視点で判断できる人選が望ましいです。 - リファレンスチェック
必要に応じて、アルムナイが在籍していた他社の関係者に話を聞くことも有効です。
受け入れ体制の整備
無事に再入社が決まった後、アルムナイがスムーズに組織に再適応(オンボーディング)できるよう、受け入れ側の体制を整えることも重要です。
- 配属部署への事前説明
アルムナイが復帰する背景や期待する役割を丁寧に説明し、歓迎ムードを作る。 - オンボーディングプログラム
退職していた期間の会社の変化(新事業、組織体制、社内ツールなど)をインプットする機会を設ける。 - メンター制度
気軽に相談できるメンター役の社員をつけることで、心理的な孤立を防ぐ。
「戻ってきたら浦島太郎状態だった…」という事態を避ける配慮が、定着率を高めます。
就業規則・規程への明記
最後に、ここまでに決めた内容を就業規則や個別の規程として明文化します。これにより、アルムナイ採用が正式な社内制度として位置づけられ、運用の安定性と公平性が担保されます。
<規程に盛り込むべき主な項目>
- 第1条(目的)
この規程の目的 - 第2条(定義)
アルムナイの定義 - 第3条(対象者)
制度の対象となる元従業員の条件 - 第4条(登録手続き)
アルムナイ・ネットワークへの登録方法など - 第5条(再雇用の手続き)
選考プロセスや採用基準 - 第6条(労働条件)
給与、役職、勤続年数の取り扱いなど - 第7条(その他)
秘密保持義務など
専門家(社会保険労務士など)に相談しながら、自社の実態に合った規程を作成しましょう。
アルムナイ採用を形骸化させない!成功させるための3つのポイント
制度は作って終わりではありません。ここでは、制度を魂の入ったものにし、アルムナイ採用を真に成功させるための運用上のポイントを3つご紹介します。
退職体験(Off-boarding)を向上させる
アルムナイ採用の本当のスタートは「退職時」にあります。退職者に対して、「いつでも戻ってきてほしい」というメッセージを伝え、円満な関係を築くことが、将来の復帰に繋がる最も重要な要素です。
- 退職者面談の実施
退職理由を真摯にヒアリングし、感謝と激励の言葉を伝える。 - 温かい送り出し
最終出社日に壮行会を開くなど、気持ちよく送り出す文化を作る。
「辞めるときに嫌な思いをした会社に戻りたい」と思う人はいません。退職者を大切にすることが、巡り巡って未来の採用力に繋がるのです。
既存社員への丁寧な説明と公平性の担保
アルムナイ採用が失敗する最大の要因は、既存社員の不満です。制度を導入する際は、その背景や目的、会社にとってのメリットを丁寧に説明し、全社的な理解を得る努力を怠らないようにしましょう。
特に、待遇面での不公平感はモチベーションの低下に直結します。なぜその待遇が妥当なのかを客観的な基準で示し、誰もが納得できる透明性の高い運用を心がけてください。
アルムナイとの継続的なコミュニケーション
アルムナイ・ネットワークは、一度作ったら終わりではありません。退職後も継続的にコミュニケーションを取り、良好な関係を維持することが重要です。
- 会社の近況や求人情報を定期的に発信する。
- アルムナイ限定のイベントや勉強会を企画する。
- 現役社員との交流の機会を設ける。
こうした地道な活動が、アルムナイの「自社への帰属意識」を育み、「いざという時に頼れる存在」として会社の採用力を下支えしてくれます。
【関連】アルムナイ採用はネットワークが9割!退職者と良好な関係を築く5つのステップと具体的施策
おすすめのアルムナイ採用を支援するサービス「リファアルム」

リファアルムは、リファラル採用とアルムナイ採用を同時に支援するサービスです。採用は感覚的に行うものではなく、全従業員を巻き込み、「全社一丸」となって取り組むことが大切です。「リファアルム」を使うことにより、従業員のリファラル採用やアルムナイ採用に対する「前向きな姿勢」を引き出すことが可能です。
1、従業員が「リファラル」「アルムナイ」に積極的に協力する、魅力的なカルチャーを形成できる。
2、創業以来のノウハウを活かし、「リファラル」「アルムナイ」だけではない採用活動全体の成功を支援。
3、協力してくれた従業員に対し、業界トップクラスのギフトラインナップで謝礼を提供。
アルムナイ採用でお困りの企業様は、「リファアルム」にお問い合わせください
本記事では、アルムナイ採用の制度設計について、準備段階から具体的なステップ、そして成功のための運用ポイントまでを網羅的に解説しました。
アルムナイ採用は、単に人手不足を補うための採用手法ではありません。退職者との縁を大切にし、人と人との繋がりを企業の資産と考える、新しい時代の経営戦略です。
しかし、「アルムナイ採用について、専門家のアドバイスが欲しい」
「アルムナイ採用を始めたいが、何から手を付けたら良いか分からない」
といったお悩みをお持ちの採用担当者様も多いのではないでしょうか。
そのようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ弊社の「リファアルム」にご相談ください。
ただツールを入れてもリファラル、アルムナイ採用が増えるとは限りません。
当社では経験豊富な採用コンサルタントが設計から運用までワンストップで支援します。
リファラル、アルムナイ採用成功のために必要なノウハウと実務支援、マネジメントをプロの人事チームが顧客の採用成功まで伴走します。
アルムナイ採用、そして採用活動全体でお困りのことがございましたら、まずはお気軽に下記よりお問い合わせください。
