アルムナイ採用の注意点7選!導入前に押さえるべきポイントを徹底解説
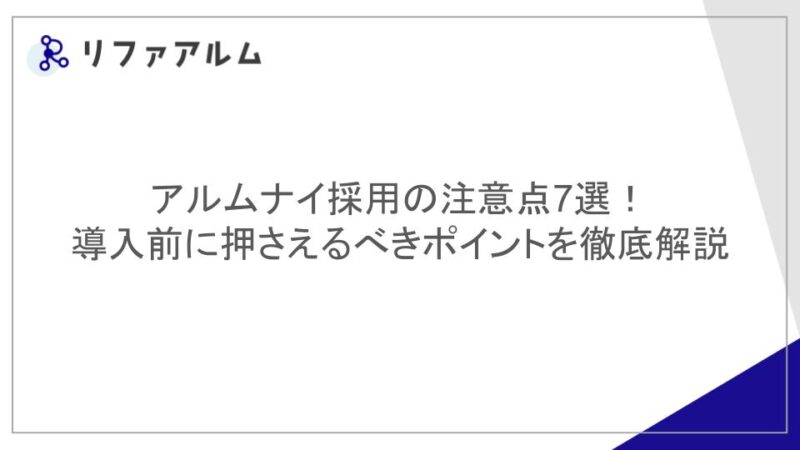
深刻化する人材不足を背景に、多くの企業が新たな採用手法に注目しています。その中でも、企業の「卒業生」である退職者を再雇用する「アルムナイ採用」は、即戦力の確保や採用コストの削減といったメリットから、導入を検討する企業が増えています。
アルムナイ採用は、企業文化への理解が深く、ミスマッチが起こりにくい非常に魅力的な手法です。しかし、その一方で、導入前に知っておくべき「注意点」も存在します。
計画なく安易に進めてしまうと、「既存社員のモチベーションが下がってしまった」「せっかく戻ってきてくれたのに、またすぐに辞めてしまった」といった、予期せぬ失敗につながる可能性も少なくありません。
そこで本記事では、アルムナイ採用を成功に導くために、導入前に必ず押さえておきたい7つの注意点と、その具体的な対策を徹底解説します。この記事を読めば、アルムナイ採用の潜在的なリスクを未然に防ぎ、安心して制度を導入・運用できるようになります。
もくじ
アルムナイ採用とは?
「アルムナイ(alumni)」とは、もともと「卒業生」や「同窓生」を意味する言葉です。ここから転じて、企業の退職者を「卒業生」と捉え、退職後も良好な関係性を維持し、再び自社で活躍してもらう採用活動を「アルムナイ採用」と呼びます。
これは、単に欠員補充のために元社員を呼び戻す「出戻り採用」とは一線を画します。企業と退職者が対等なパートナーとしてつながり続ける、戦略的な採用手法の一つです。
アルムナイ採用におけるメリット
アルムナイ採用には、主に4つの大きなメリットがあります。
- 即戦力としての活躍
企業文化や事業内容、業務の流れを既に理解しているため、入社後の立ち上がりが非常に早く、即戦力としての活躍が期待できます。 - 採用・教育コストの削減
人材紹介会社への手数料や求人広告費といった外部コストを大幅に削減できます。また、基本的なビジネスマナーや社内ルールに関する研修も不要なため、教育コストも抑えられます。 - ミスマッチの低減
働く環境や人間関係、業務内容をお互いがある程度理解しているため、「こんなはずじゃなかった」という入社後のミスマッチが起こりにくく、高い定着率が見込めます。 - 社外の知見によるイノベーション促進
アルムナイ人材が他社で培った新しいスキルやノウハウ、異なる視点を社内に持ち込むことで、組織が活性化し、新たなイノベーションが生まれるきっかけにもなります。
【関連】リファラル採用のメリット7選!デメリットや成功のコツも徹底解説
アルムナイ採用における注意点7選
多くのメリットがあるアルムナイ採用ですが、成功させるための7つの注意点を紹介します。既存社員との間に不公平感や軋轢が生まれる
- なぜ問題か?
最も配慮すべきなのが、既存社員との関係性です。例えば、アルムナイ人材が退職前より高い役職や給与で復帰した場合、長年会社に貢献してきた社員が「なぜ出戻りの人が自分より優遇されるのか」と不公平感を抱く可能性があります。こうした不満は、モチベーションの低下や人間関係の悪化を招き、組織全体の生産性を下げる原因となります。 - どう対策するか?
・公平な評価・待遇基準の明確化:アルムナイ人材の待遇は、他社での経験やスキルを客観的に評価した上で決定し、その基準を既存社員にも説明できるようにしておくことが重要です。明確で公平な評価制度を事前に整備・公開しましょう。
・丁寧な事前説明:受け入れ部署のメンバーには、採用の経緯や本人に期待する役割を事前に丁寧に説明し、理解を求めましょう。「会社の成長のために、彼の力が必要だ」というポジティブなメッセージを伝えることが大切です。
【関連】アルムナイ採用を社内で成功させる方法は?導入の進め方と説得のコツ
退職理由が解消されていない場合の「再退職」リスク
- なぜ問題か?
「給与が低い」「残業が多い」「人間関係に問題があった」など、退職に至った根本的な原因が解消されていなければ、復帰後に同じ不満を抱き、再び退職してしまうリスクが非常に高くなります。 - どう対策するか?
・退職理由の深いヒアリング:選考の段階で、当時の退職理由を正直に話してもらいましょう。そして、その原因となった課題が現在、社内でどのように改善されているかを具体的に伝えることが不可欠です。もし課題が残っている場合は、その事実も誠実に伝え、お互いの認識をすり合わせる必要があります。
「昔のやり方」への固執と変化への不順応
- なぜ問題か?
本人の在籍期間が長かった場合ほど、「昔はこうだった」という過去の成功体験ややり方に固執してしまうことがあります。その結果、退職期間中に導入された新しい社内ルールや業務フロー、ITツールに馴染めず、周囲との軋轢を生んでしまうケースです。 - どう対策するか?
・オンボーディングの実施:アルムナイ人材も「中途採用者の一人」と捉え、他の社員と同様にオンボーディング(受け入れ研修)を必ず実施しましょう。会社の現状や変化点、新しいルールなどをインプットする機会を設けることが重要です。
・メンター制度の導入:気軽に質問や相談ができるメンター役の社員をつけることで、本人の心理的な孤立を防ぎ、新しい環境へのスムーズな適応をサポートできます。
出戻り人材に対する「過度な期待」
- なぜ問題か?
経営者や人事が「元社員だから大丈夫だろう」「すぐに成果を出してくれるはずだ」と期待しすぎるあまり、本人に過度なプレッシャーを与えてしまったり、逆に十分なサポートを怠ってしまったりするケースがあります。 - どう対策するか?
・現実的な期待値の共有:受け入れ部署の上司や同僚には、本人に期待する役割を伝えつつも、過度な期待はせず、他のメンバーと同じようにサポートするよう協力を仰ぎましょう。
・定期的な1on1ミーティング:入社後は、定期的に1on1ミーティングの場を設け、本人が抱える課題や悩み、コンディションを把握し、早期にフォローできる体制を整えましょう。
アルムナイ・ネットワークの構築・運用コスト
- なぜ問題か?
アルムナイ採用を本格的に行うには、退職者との継続的な接点を持つための「アルムナイ・ネットワーク」の構築が必要です。しかし、このネットワークの運営には、SNSの更新、交流イベントの企画、名簿の管理など、相応のマンパワーや時間、場合によってはコストがかかります。 - どう対策するか?
・スモールスタートを心がける:最初から大規模な仕組みを目指す必要はありません。まずはFacebookグループやメーリングリストの作成など、低コストで始められる方法から試してみましょう。自社のリソースに見合った、継続可能な運用方法を見つけることが大切です。
ネガティブな退職者の影響
- なぜ問題か?
全ての退職者が、会社に対してポジティブな感情を抱いているとは限りません。もし、会社に不満を持って辞めた人がネットワーク内にいると、SNSなどでネガティブな情報を発信し、企業の評判を下げたり、他のアルムナイ候補者の復帰意欲を削いだりする可能性があります。 - どう対策するか?
・円満退職を促すオフボーディング:退職時の手続きや面談(オフボーディング)を丁寧に行い、従業員が「この会社で働けて良かった」と感じられるような円満退職を心がけることが、将来のアルムナイ採用の第一歩です。
・コミュニティのルール作り:ネットワークへの参加は任意とし、他者への誹謗中傷を禁止するなど、コミュニティの健全性を保つための簡単なルールを設けておくと良いでしょう。
採用基準の曖昧化
- なぜ問題か?
「元社員だから」「人柄はよく知っているから」という情実や安心感から、採用基準が甘くなってしまう危険性があります。その結果、現在の事業フェーズで本当に必要とされるスキルや経験を持たない人材を採用してしまい、ミスマッチにつながるケースです。 - どう対策するか?
・客観的な選考プロセスの実施:アルムナイ採用であっても、通常の採用プロセスと同様に、複数人での面接を実施しましょう。他社での経験や身につけたスキルを客観的に評価し、自社で再び活躍できる人材かどうかを冷静に見極めることが重要です。
アルムナイ採用を成功させるための導入ステップ
アルムナイ採用の注意点を踏まえた上で、実際にアルムナイ採用を導入するにはどうすればよいのでしょうか。
制度設計と社内への周知
まずは、アルムナイ採用の土台となるルール作りから始めます。
- 採用基準の明確化
どのような役職・スキルを持つ人材を対象とするか。 - 待遇・評価のルール作り
他社での経験をどのように評価し、給与や役職に反映させるか。 - 受け入れ体制の整備
オンボーディングやメンター制度をどうするか。 これらのルールを文書化し、関係者間で共有します。同時に、制度導入の目的やメリット、懸念される注意点への対策などを既存社員へ丁寧に説明し、全社的な理解と協力を得ることが成功の鍵です。
退職者との継続的な関係構築(ネットワーク作り)
次に、退職者とつながるためのプラットフォームを準備します。中小企業であれば、まずは担当者が管理できる範囲で、Facebookの非公開グループを作成したり、個別に連絡先をリスト化したりすることから始めるのが現実的です。 企業の近況や求人情報を定期的に発信するなど、退職後も「つながっている」という意識を持ってもらうことが大切です。
丁寧な選考と受け入れ体制の構築
実際に復帰を希望するアルムナイが現れたら、注意深く選考を進めます。特に、退職理由や他社での経験、復帰後にどのようなキャリアを築きたいかを深くヒアリングする面接が重要です。 採用が決まったら、受け入れ部署と連携し、オンボーディングの準備やメンターのアサインなど、スムーズに業務を再開できる環境を整えておきましょう。
【関連】アルムナイ採用の待遇はどう決める?適切な決め方と注意点を解説
アルムナイ採用に特化したツール導入による情報のデータベース化
円満退職者の連絡先、在籍時の役職や実績、退職理由などを本人の同意を得た上でデータベース化し、いつでも連絡が取れる状態を維持します。
また、アルムナイ採用ツールを導入することで、アルムナイとのコミュニケーションを円滑化し、アルムナイ採用の成功へと導くことができます。
【関連】アルムナイ採用を成功に導くツールとは?メリット・機能から導入の注意点まで解説
おすすめのアルムナイ採用を支援するサービス「リファアルム」

リファアルムは、リファラル採用とアルムナイ採用を同時に支援するサービスです。採用は感覚的に行うものではなく、全従業員を巻き込み、「全社一丸」となって取り組むことが大切です。「リファアルム」を使うことにより、従業員のリファラル採用やアルムナイ採用に対する「前向きな姿勢」を引き出すことが可能です。
1、従業員が「リファラル」「アルムナイ」に積極的に協力する、魅力的なカルチャーを形成できる。
2、創業以来のノウハウを活かし、「リファラル」「アルムナイ」だけではない採用活動全体の成功を支援。
3、協力してくれた従業員に対し、業界トップクラスのギフトラインナップで謝礼を提供。
アルムナイ採用でお困りの企業様は、「リファアルム」にお問い合わせください
本記事では、アルムナイ採用を導入する上での7つの注意点と、その対策、そして具体的な導入ステップについて解説しました。
アルムナイ採用は、単に「人手不足を補うための出戻り採用」ではありません。注意点を正しく理解し、既存社員への配慮を忘れず、戦略的に運用することで、企業と退職者の双方が成長できる、非常に価値のある採用手法となります。
しかし、「アルムナイ採用について、専門家のアドバイスが欲しい」
「アルムナイ採用を始めたいが、何から手を付けたら良いか分からない」
といったお悩みをお持ちの採用担当者様も多いのではないでしょうか。
そのようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ弊社の「リファアルム」にご相談ください。
ただツールを入れてもリファラル、アルムナイ採用が増えるとは限りません。
当社では経験豊富な採用コンサルタントが設計から運用までワンストップで支援します。
リファラル、アルムナイ採用成功のために必要なノウハウと実務支援、マネジメントをプロの人事チームが顧客の採用成功まで伴走します。
アルムナイ採用、そして採用活動全体でお困りのことがございましたら、まずはお気軽に下記よりお問い合わせください。
