アルムナイ採用の待遇はどう決める?適切な決め方と注意点を解説
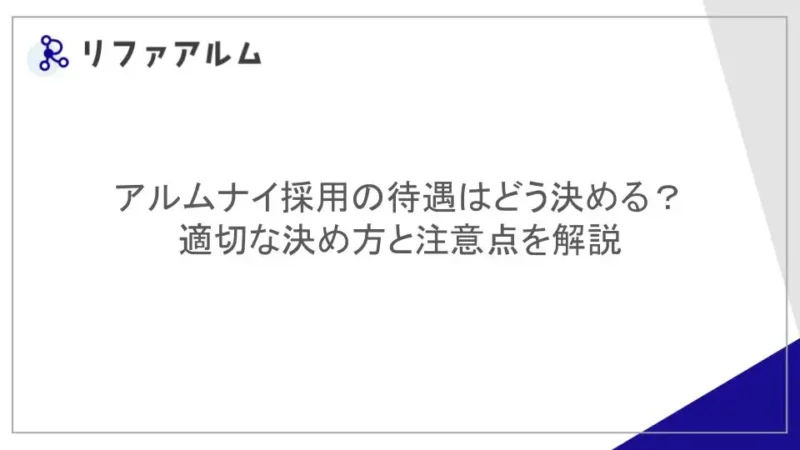
「募集をかけても、なかなか良い人材からの応募がない…」 「採用コストは増える一方なのに、求める人材は採用できない…」
多くの企業が、このような採用に関する深刻な悩みを抱えています。この慢性的な人材不足の解決策として、今、「アルムナイ採用」が新たな選択肢として注目を集めています。
アルムナイ採用とは、企業の退職者を再雇用する制度のことです。即戦力としての活躍や採用コストの削減が期待できる一方で、多くの経営者様や人事担当者様が頭を悩ませるのが「待遇をどう決めるか」という問題ではないでしょうか。
この記事では、アルムナイ採用を成功させるための鍵となる「待遇」について詳しく解説します。
もくじ
アルムナイ採用とは?

待遇の話に入る前に、まずはアルムナイ採用の基本についておさらいしておきましょう。
アルムナイ採用の基礎知識
「アルムナイ(alumni)」とは、もともと「卒業生」や「同窓生」を意味する言葉です。そこから転じて、人事領域では企業の「退職者」を指す言葉として使われています。
つまりアルムナイ採用とは、自社を一度退職した人材を、再び社員として迎え入れる採用手法のことです。「出戻り採用」や「カムバック採用」と言い換えると、よりイメージしやすいかもしれません。
かつては「一度辞めた会社に戻る」ことにネガティブなイメージがありましたが、雇用の流動化が進み、転職が当たり前になった現代では、アルムナイ採用は企業と個人双方にとって合理的な選択肢の一つとして認識されつつあります。
アルムナイ採用のメリット
企業がアルムナイ採用に注目する背景には、主に3つの大きなメリットがあります。
- 即戦力としての活躍が期待できる
アルムナイは、自社の企業文化や事業内容、業務の進め方をすでに理解しています。そのため、入社後のミスマッチが起こりにくく、新たな環境に慣れるまでのオンボーディング期間も短縮できます。まさに「即戦力」として、早期の活躍が期待できるでしょう。 - 採用コストや教育コストを削減できる
アルムナイ採用は、転職サイトへの広告掲載や人材紹介会社への手数料といった外部コストがかからない場合が多く、採用コストを大幅に削減できます。また、基本的なビジネススキルや企業理念に関する研修も不要なため、教育コストの抑制にも繋がります。 - 他社の知見やノウハウがもたらされる
退職してから再入社するまでの期間に、アルムナイは他社で新たなスキルや知識、人脈を培っています。その経験を自社に持ち帰ってもらうことで、組織の活性化や新たなイノベーションの創出が期待できます。
アルムナイ採用のデメリット
もちろん、メリットばかりではありません。注意すべきデメリットも存在します。
- 既存社員のモチベーションに影響を与える可能性がある
特に待遇面で、既存社員が「なぜ辞めた人が優遇されるのか」といった不公平感を抱いてしまうケースがあります。これはアルムナイ採用で最も注意すべき点であり、本記事で詳しく解説します。 - 退職理由が解消されていないと、再度離職につながる恐れがある
人間関係や労働環境など、本人が退職を決意した根本的な原因が社内に残ったままだと、同じ理由で再び離職してしまう可能性があります。受け入れる前に、退職理由を真摯にヒアリングすることが重要です。
【関連】アルムナイ採用の導入前に知っておくべきデメリットとは?具体的な対策と成功に導くポイントを解説
アルムナイ採用における待遇の決め方
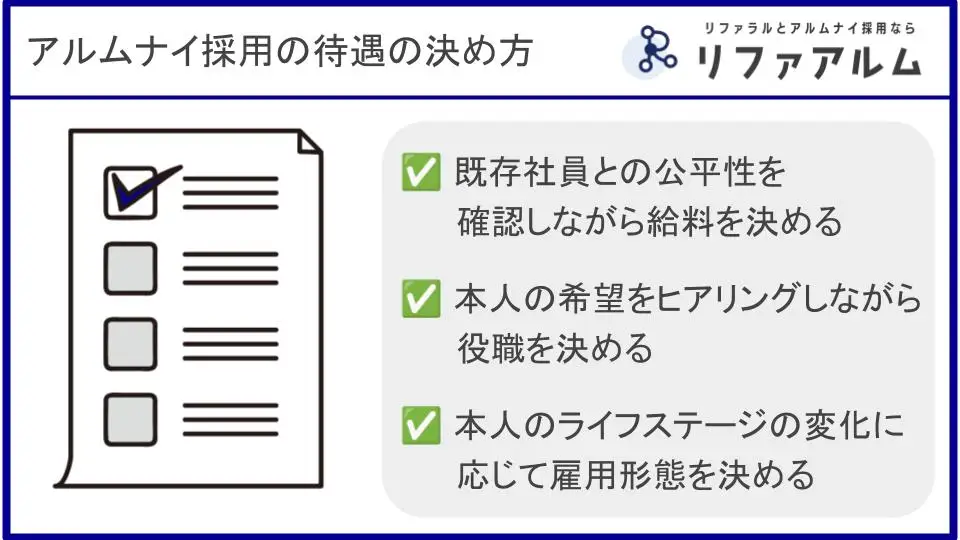
それでは、本題である待遇の決め方について見ていきましょう。 基本的な考え方は「在籍時の待遇をベースに、退職後の経験・スキルを客観的に評価する」ことです。これを念頭に、給与・役職・雇用形態の3つのケースに分けて解説します。
1. 給与の決め方
給与は、待遇の中でも最も慎重な判断が求められる要素です。以下のステップで検討しましょう。
- 在籍時の給与を基準にする
まずは、退職時の給与額を基本的なスタートラインとして設定します。 - 退職後の経験・スキルを評価し、上乗せを検討する
他社でどのような経験を積み、どんなスキルを身につけたのかを具体的に評価し、給与に反映させます。評価すべきプラスαの要素には、以下のようなものが挙げられます。
・専門スキル: プログラミング言語、Webマーケティング、高度な経理知識など
・マネジメント経験: 部下の人数、プロジェクトの規模など
・他社での役職や実績
・取得した資格 - 既存社員との公平性を確認する
算出した給与額が、社内の給与テーブルや、同程度のスキル・経験を持つ既存社員の給与水準と大きく乖離していないかを確認します。客観的な評価基準を設けることで、他の社員への説明責任を果たすことができます。
2. 役職・ポジションの決め方
役職やポジションも、本人のモチベーションや組織体制に大きく影響します。
まずは在籍時の役職を参考にしつつ、本人のキャリアプランや希望を丁寧にヒアリングすることが重要です。「どのような役割で会社に貢献したいか」という意欲を尊重しましょう。
その上で、退職後の経験で培ったリーダーシップや専門性を評価し、現在の組織図の中で最も活躍できるポジションを検討します。場合によっては、在籍時よりも上位の役職を提示することも十分に考えられます。
ただし、この場合も既存社員とのバランスへの配慮は不可欠です。「なぜこの人がこのポジションなのか」、他の社員が納得できるように説明できる明確な理由を準備しておきましょう。
3. 雇用形態・福利厚生
アルムナイ採用は、必ずしも正社員だけとは限りません。本人のライフステージの変化や希望に応じて、契約社員や業務委託、時短勤務といった柔軟な雇用形態を検討することも有効です。専門的なスキルを特定のプロジェクトで活かしてもらう、といった関わり方も可能でしょう。
福利厚生については、雇用形態に応じた社内規程に則り、原則として他の社員と同一の条件を適用するのが基本です。
アルムナイの待遇を決める際の注意点
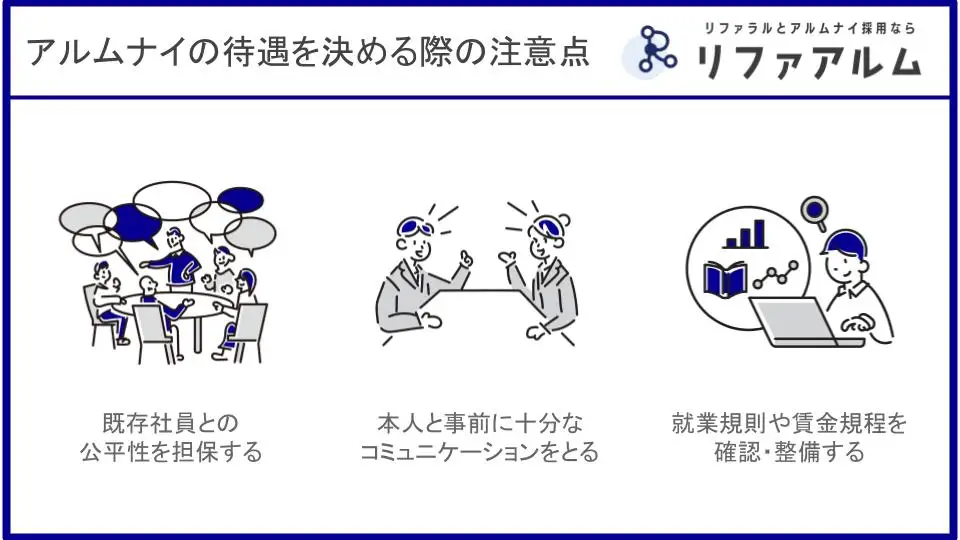
待遇決定のプロセスでつまずき、アルムナイ採用が失敗に終わるケースも少なくありません。そうした事態を避けるために、必ず押さえておきたい3つの注意点をご紹介します。
既存社員との公平性を担保する
アルムナイ採用において、最大の障壁となり得るのは既存社員の不満です。長年会社に貢献してきた社員が、「辞めて戻ってきた人の方が待遇が良い」と感じれば、モチベーションの低下や人間関係の悪化を招きかねません。
これを防ぐためには、待遇決定のプロセスを明確にし、客観的な評価基準を持つことが何よりも重要です。なぜその給与額なのか、なぜその役職なのか。その根拠を、自社の評価制度や給与テーブルと照らし合わせて、誰にでも説明できるようにしておきましょう。
本人と事前に十分なコミュニケーションをとる
企業側とアルムナイ本人との間で、待遇に関する期待値にズレが生じているケースも散見されます。企業側は「戻ってきてくれるだけでありがたい」と思っていても、本人は「他社での経験を高く評価してほしい」と考えているかもしれません。
こうしたミスマッチを防ぐため、オファー面談などの機会を設け、給与・役職・業務内容について丁寧にすり合わせを行いましょう。お互いが納得した上で入社してもらうことが、その後の活躍を後押しします。
就業規則や賃金規程を確認・整備する
自社の就業規則に、再雇用に関する規定があるかを確認しましょう。特に、退職金の取り扱いや勤続年数の考え方(在籍期間を通算するかどうかなど)は、後々トラブルになりやすいポイントです。
もし規定がない場合は、アルムナイ採用を本格的に導入するタイミングで、規程を整備しておくことを強く推奨します。法的な観点からも、明確なルールを定めておくことが企業のリスク管理に繋がります。
アルムナイ採用を成功へ導くポイント
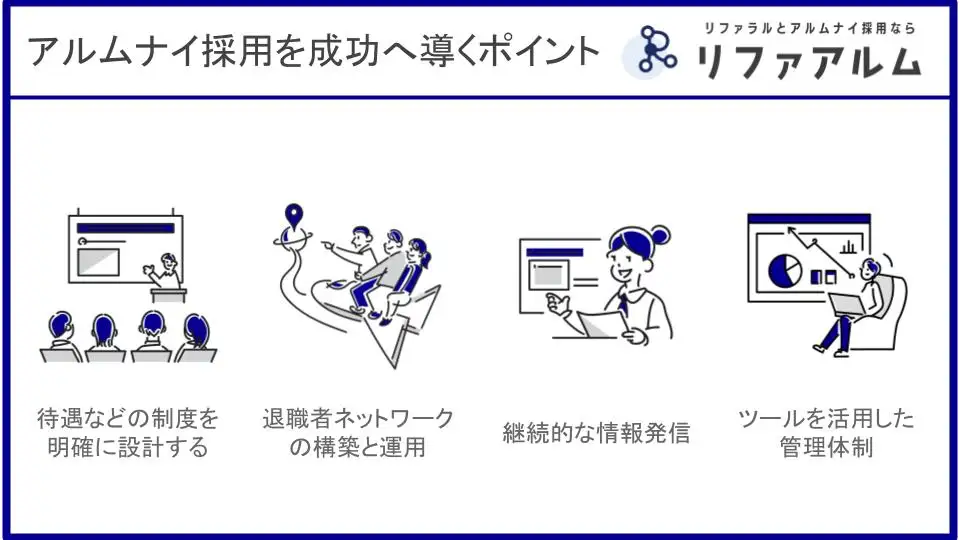
ここまで待遇の決め方や注意点を解説してきましたが、アルムナイ採用は、待遇さえ決めれば成功するわけではありません。場当たり的な運用ではなく、戦略的な仕組みとして社内に定着させることが重要です。 ここでは、施策全体を成功に導くための4つのポイントをご紹介します。
1. 待遇などの制度を明確に設計する
アルムナイ採用を単発のイベントで終わらせず、継続的な採用チャネルとして機能させるためには、制度としての設計が不可欠です。 「どのような経験を積んだアルムナイを」「どのようなプロセスを経て」「どのような待遇で」迎え入れるのか。そのルールを明文化しておきましょう。担当者が変わっても運用できる再現性のある制度を構築することで、公平性と透明性が担保され、既存社員の納得感にも繋がります。
【関連】アルムナイ採用を成功させる制度とは?具体的な設計方法と運用のコツ
2. 退職者ネットワークの構築と運用
退職したアルムナイと接点がなければ、採用の機会は生まれません。まずは、退職者と繋がり続けるための「ネットワーク」を構築しましょう。 具体的には、退職者専用のSNSグループ(FacebookやLinkedInなど)やメーリングリストを作成し、参加を促すのが有効です。もちろん、こうした取り組みの前提として、社員が「辞めた後も繋がり続けたい」と思えるような良好な関係性を、在籍中から築いておくことが最も重要です。
3. 継続的なコミュニケーションと情報発信
ネットワークを構築したら、それを維持・活性化させるための継続的な働きかけが求められます。会社の近況や新たな取り組み、募集中のポジションといった情報を定期的に発信しましょう。 「いつでも戻ってこれる場所である」「あなたの力をまた貸してほしい」というメッセージを伝え続けることで、アルムナイが転職を考えた際に、自社を真っ先に思い出してくれる可能性が高まります。
4. ツールを活用した管理体制も
退職者が増えてくると、誰がどこで何をしているのか、Excelやスプレッドシートでの管理には限界がきます。 近年では、アルムナイの情報を一元管理し、コミュニケーションを効率化する専門のクラウドサービスも登場しています。こうしたツールを活用することで、情報管理の負担を軽減し、戦略的なアプローチ漏れを防ぐことができます。まずは小規模からでも、管理体制を整えていく意識が大切です。
【関連】アルムナイ採用を成功に導くツールとは?メリット・機能から導入の注意点まで解説
おすすめのアルムナイ採用を支援するサービス「リファアルム」

リファアルムは、リファラル採用とアルムナイ採用を同時に支援するサービスです。採用は感覚的に行うものではなく、全従業員を巻き込み、「全社一丸」となって取り組むことが大切です。「リファアルム」を使うことにより、従業員のリファラル採用やアルムナイ採用に対する「前向きな姿勢」を引き出すことが可能です。
1、従業員が「リファラル」「アルムナイ」に積極的に協力する、魅力的なカルチャーを形成できる。
2、創業以来のノウハウを活かし、「リファラル」「アルムナイ」だけではない採用活動全体の成功を支援。
3、協力してくれた従業員に対し、業界トップクラスのギフトラインナップで謝礼を提供。
アルムナイ採用でお困りの企業様は、「リファアルム」にお問い合わせください
本記事では、アルムナイ採用における待遇の決め方から、施策を成功させるための具体的なポイントまでを解説しました。
アルムナイは、あなたの会社の文化と外部の知見を併せ持つ、他に代えがたい貴重な人材です。適切な待遇と、いつでも戻ってこれる仕組みを用意して誠意を伝えることができれば、アルムナイ採用は単なる人手不足の解消策に留まりません。企業に新たな活気をもたらし、成長を加速させるための「戦略的一手」となり得るのです。
しかし、「アルムナイ採用の待遇についてさらに詳しく知りたい」
「アルムナイ採用を始めたいが、何から手を付けたら良いか分からない」
といったお悩みをお持ちの採用担当者様も多いのではないでしょうか。
そのようなお悩みをお持ちでしたら、ぜひ弊社の「リファアルム」にご相談ください。
ただツールを入れてもリファラル、アルムナイ採用が増えるとは限りません。
当社では経験豊富な採用コンサルタントが設計から運用までワンストップで支援します。
リファラル、アルムナイ採用成功のために必要なノウハウと実務支援、マネジメントをプロの人事チームが顧客の採用成功まで伴走します。
アルムナイ採用、そして採用活動全体でお困りのことがございましたら、まずはお気軽に下記よりお問い合わせください。
